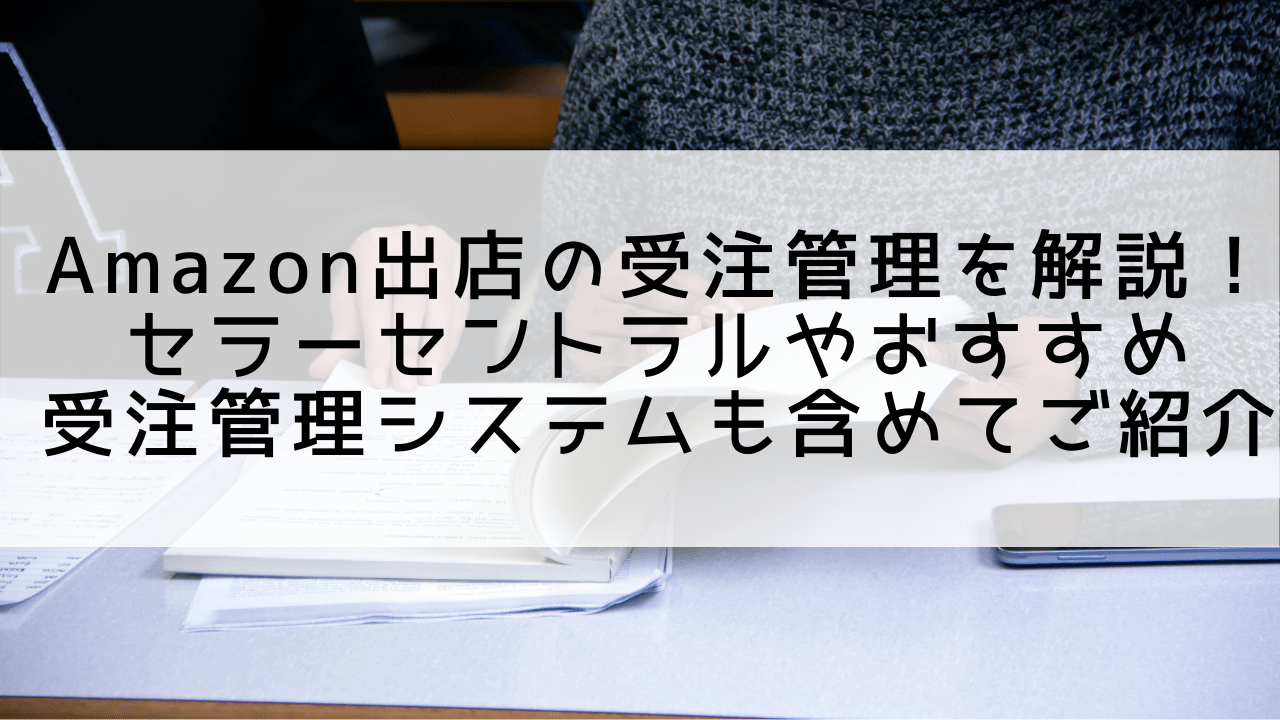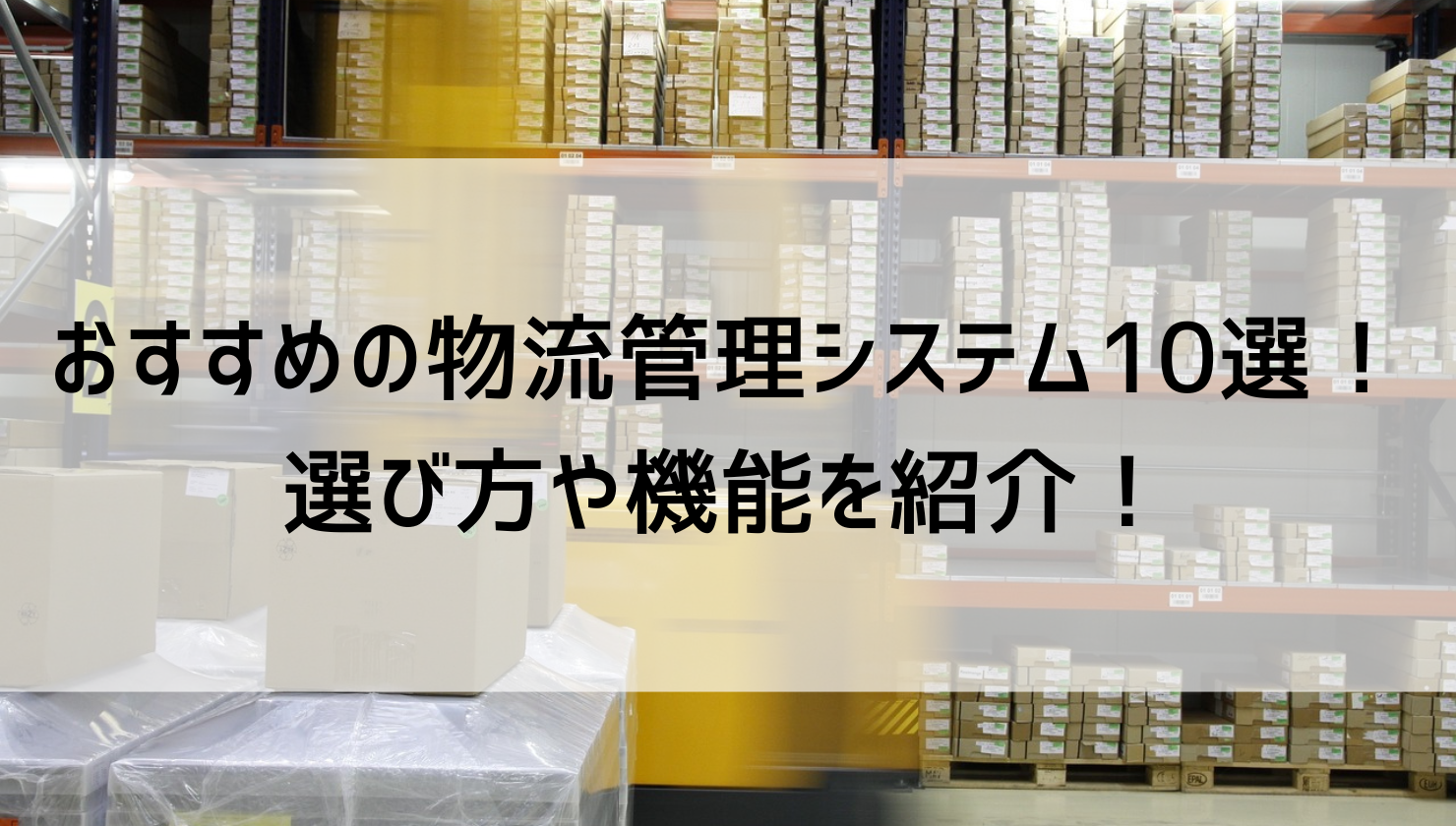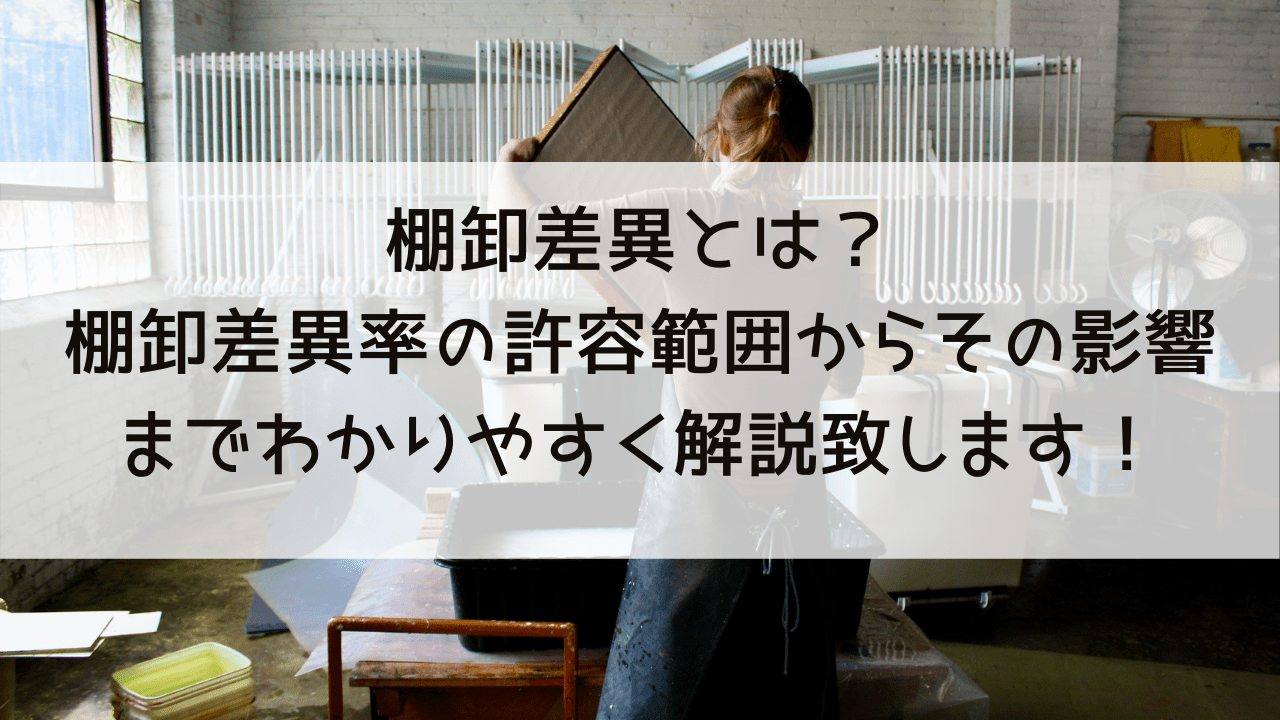おすすめの雑貨の物流代行は?雑貨物流代行にはどんな特徴がある?と気になっていませんか。
結論、おすすめの雑貨物流代行は下記のとおりです。
- ・mylogi(アートトレーディング)
- ・MOTOMURA
- ・スクロール360
- ・富士ロジテックホールディングス
- ・Sendon.com
- ・BeeCruise
雑貨物流代行の特徴は、多品種少量への柔軟対応、ギフトやセット販売に必要な流通加工、シーズンやトレンドに合わせた入れ替え対応、壊れやすい商品の破損防止や適切な梱包設計、さらにECと実店舗の両方に最適化された配送体制を備えている点にあります。
この記事ではほかにも雑貨物流代行の選び方や利用するメリットデメリットなども詳しく解説していきます。是非参考にしてくださいね。
雑貨の物流代行とは?
雑貨の物流代行とは、企業や個人が販売する雑貨商品の在庫管理・梱包・出荷作業などを専門業者に委託するサービスのことです。
自社で倉庫を持たずに済むため、固定費を大幅に削減でき、注文数の増減に合わせて柔軟に対応できるのが大きな特徴です。
特に雑貨はサイズや形状が多様で、壊れやすい商品も少なくありません。そのため、物流代行会社では丁寧な検品・適切な梱包・配送方法の選定を行い、顧客満足度を高めるサポートをしています。
さらに、ECサイトとのシステム連携や出荷スピードの向上など、効率化に欠かせない仕組みも整っています。
物流代行を活用することで、販売者は商品企画やマーケティングに注力できる環境を整えられるため、事業成長の加速につながるのです。
雑貨物流代行の特徴
雑貨の物流には多品種少量やギフト需要など特有の要件があり、一般的な物流とは異なる運用設計が求められます。
ここでは、実務で重要となるポイントを整理し、次の見出しで具体的な対応内容を解説します。
多品種少量への柔軟対応
雑貨物流では、幅広いアイテムを少量ずつ効率的に扱うことが欠かせません。そのため、多品種少量の特性に合わせた柔軟な対応力が重要になります。詳しい内容を次から見ていきましょう。
SKU数が多い商品の取り扱い
雑貨は種類が非常に多く、SKU数も膨大になります。そのため、一度に大量出荷するのではなく、少量多品種に対応できる体制が必要です。
小ロット出荷の効率化
1注文あたりの数量が少ないケースでも、迅速かつ正確に出荷できるよう仕組みが整っていることがポイントです。
流通加工の幅広さ
雑貨はギフトやセット商品として販売されるケースが多いため、流通加工の幅広さが求められます。多様な顧客ニーズに応じて、きめ細やかな作業に対応できるかが鍵です。詳しい内容を次から見ていきましょう。
ラッピングや熨斗対応
ギフト需要に応じて、ラッピングや熨斗のセットアップに対応できるのが雑貨物流の特徴です。
セット組・アソート対応
複数の商品を組み合わせたギフトセットやアソート商品を柔軟に加工できる仕組みも重要です。
季節・トレンド商品の入れ替え頻度
雑貨はシーズンやトレンドによって商品の需要が大きく変動します。そのため、入れ替えの頻度に対応できる物流体制が必要です。詳しい内容を次から見ていきましょう。
季節商材の大量入庫
クリスマスやバレンタインなど、シーズンごとに商品が一気に入庫するため、その都度効率的に対応できる力が求められます。
短いライフサイクルへの対応
流行やトレンドの変化が早い雑貨に合わせて、スピーディに在庫を入れ替える体制が必要です。
破損防止や梱包方法の工夫
陶器やガラス製など壊れやすい雑貨は、破損防止の工夫が必須です。商品特性を理解した梱包が物流品質を大きく左右します。詳しい内容を次から見ていきましょう。
緩衝材や専用梱包資材の活用
雑貨は壊れやすいものが多いため、緩衝材や専用資材を活用して配送中の破損を防ぐ工夫が必要です。
商品特性に応じた梱包設計
ガラス製品や陶器など、アイテムごとの特性を踏まえた梱包設計を行うことで、返品リスクを軽減できます。
EC・実店舗両方への対応力
雑貨はオンライン販売と店舗販売の両方で扱われることが多く、それぞれに最適化された物流対応が求められます。詳しい内容を次から見ていきましょう。
EC向け個別配送
個人顧客への宅配を前提にしたピッキング・梱包体制を整えることが重要です。
店舗向け一括納品
実店舗用には一括出荷や店頭陳列を意識した梱包が求められ、両立できる体制が強みになります。
雑貨物流代行の選び方
委託先によって得意分野や提供範囲は大きく異なります。自社の商品特性や販売チャネルに合うかを軸に、対応力やコストだけでなく運用の柔軟性まで確認しましょう。以下の観点を順にチェックしていきます。
幅広い商品カテゴリへの対応力
雑貨物流代行を選ぶ際は、その会社がどれだけ多様な雑貨を取り扱った経験を持っているかが重要です。雑貨はカテゴリーが幅広いため、専門性が高いほど安心して任せられます。詳しい内容を次から見ていきましょう。
多品種対応の経験
インテリア雑貨や文房具、日用品など幅広い分野の取り扱い実績があるかを確認しましょう。
業界特有の課題への理解
壊れやすさや流行の変化など、雑貨特有の課題に対応できる知識と経験があるかが大切です。
付加価値サービスの充実度
雑貨はギフト需要や販促用途が多く、流通加工の柔軟さが選定のカギとなります。自社の販売形態に合わせて対応してもらえるかを見極めましょう。詳しい内容を次から見ていきましょう。
ギフトラッピング対応
贈答用のラッピングや熨斗対応ができるかどうかは重要な選定ポイントです。
販促用セット組
複数の商品を組み合わせたキャンペーンやアソート販売に対応できると販路が広がります。
需要変動への強さ
雑貨はシーズンやイベントで需要が急増するため、繁忙期に安定した出荷ができるかどうかが重要です。キャパシティ不足は納期遅延につながるため注意が必要です。詳しい内容を次から見ていきましょう。
繁忙期の増員体制
人員を臨機応変に増やせるかどうかで、スムーズな出荷ができるかが決まります。
急な出荷増への柔軟性
急激に注文が増えても柔軟に対応できるシステムやノウハウが整っているかを確認しましょう。
在庫・システムの精度
多品種を扱う雑貨物流では、在庫管理の精度とシステム連携の強さが業務効率を左右します。リアルタイムに正確な情報を把握できるかを確認することが大切です。詳しい内容を次から見ていきましょう。
在庫精度の高さ
入出庫や棚卸で誤差が少なく、常に正しい在庫数を把握できるかが重要です。
ECシステムとの連携
受注管理システムやカートと自動連携できることで、出荷までのスピードと精度が高まります。
コストと安心のサポート力
雑貨物流は加工や梱包にコストがかかりやすいため、料金体系のわかりやすさとサポート力が選定の基準となります。長期的に安心して任せられるパートナーかどうかを見極めましょう。詳しい内容を次から見ていきましょう。
料金体系の明確さ
初期費用や作業費、保管料などのコストが分かりやすく提示されているかが大切です。
専任担当者の有無
物流課題に対して相談できる専任担当者がいると、突発的な問題にも安心して対応できます。
小規模~中規模事業者におすすめの雑貨物流代行会社
初めての委託やスモールスタートには、きめ細かな対応と小ロット運用に強いパートナーが適しています。次に紹介する企業は、少量多品種や突発的な作業にも柔軟に寄り添える点が魅力です。
mylogi(アートトレーディング)

mylogi(アートトレーディング)は「伴走型フルフィルメント」を掲げ、単なる物流アウトソースではなく、お客様に寄り添った細やかな対応を強みとしています。
小ロット出荷・丁寧な梱包・臨機応変な受注対応を得意とし、スタートアップや成長過程のEC事業者に最適なパートナーです。雑貨や日用品などSKU数が多く出荷数の少ない商材にも対応し、ラッピングや同梱物の挿入など販促面でのサポートも可能です。
専任担当者によるきめ細やかなサポートと、大きな安心を届ける現場体制で、顧客満足度の向上に直結。柔軟なサービスで事業成長をしっかり支える物流代行、それがmylogiです。
\物流代行に関する無料相談は/
MOTOMURA

雑貨EC事業者の物流パートナーとして信頼を集めるのが「株式会社MOTOMURA」です。
入荷から出荷・返品までの一連業務をワンストップで代行し、小ロットや多品種にも柔軟に対応。
14時までの注文は当日出荷可能で、土日祝の発送にも対応。
首都圏拠点によるコストパフォーマンスの高さと、システム連携による正確な在庫管理も魅力。
初めて物流代行を検討する企業にもおすすめの一社です。
大規模事業者におすすめの雑貨物流代行会社
出荷量が多くKPIで厳密に管理したい場合は、システム基盤や自動化設備を備えた大規模対応型が有力候補です。以下では、通販全体を包括支援できる企業や高度なオペレーションで拡張性を確保できる企業を紹介します。
スクロール360

通販業務全体をワンストップで支援する「スクロール360」は、大規模な雑貨EC事業者にとって強力なパートナーです。
物流代行だけでなく、EC運営代行や受注対応、マーケティングまで一気通貫で対応可能。
グループ会社の実績に基づく高い運用力とKPI管理により、売上成長と業務効率化の両立を実現します。
多店舗展開・モール運営に課題を感じている企業には特におすすめです。
富士ロジテックホールディングス

成長著しい通販業界の中で、高品質な物流体制を求める大規模事業者におすすめなのが富士ロジテックホールディングスです。
20年以上の実績を活かし、自動仕分けロボットt-Sortや音声ピッキングVIPSなど最先端技術を導入。
自社開発WMSにより多拠点・多商品に対応可能で、誤出荷防止・人手不足対策・生産性向上をトータルで実現します。
物流業務の効率化と高精度なオペレーションを求める企業に最適なパートナーです。
海外発送でおすすめの雑貨物流代行会社
越境販売や海外向け配送では、通関や多通貨決済、現地サポートなど国内とは異なるノウハウが不可欠です。ここからは、海外発送をスムーズに進められるサービスを取り上げます。
Sendon.com

日本から世界各地へ商品を届けたい方におすすめの海外発送代行サービスが「Sendon.com」です。
会員登録後は3ステップで発送可能。90日間無料保管や多通貨・多決済対応、ネイティブ対応のカスタマーサポートなど、海外ユーザーにもやさしい設計が魅力です。
日本のECサイトで購入した商品を手軽に海外発送したい個人・法人双方に対応。スピード・安心・コストのバランスが取れたサービスです。
BeeCruise

越境ECや海外発送に強みを持つ「BeeCruise」は、1件から利用可能な国際配送代行サービスを提供しており、初めての海外発送にも安心して利用できる体制が整っています。
長年の実績とBEENOSグループのグローバルネットワークを活かし、低コストかつスピーディーな国際物流を実現。
「海外展開を始めたいが何から手を付ければ良いか分からない」といった企業にも、専門スタッフが丁寧にサポートしてくれるおすすめのパートナーです。
雑貨物流代行にかかる費用
雑貨の物流代行にかかる費用は初期費用と月次の固定費、出荷量に応じた変動費、オプションの加工費に大別されます。相場感と内訳を押さえておくことで、無理のない委託設計と予算管理が可能になります。各項目を順に見ていきましょう。
初期費用
初期費用の相場料金は0~10万円程度です。
初期費用は、物流代行サービスを導入する際に最初に発生する初期投資です。
倉庫管理システム(WMS)の初期設定やアカウント登録、商品マスタやSKUの登録、運用フロー設計などが主な対象となります。
雑貨物流は多品種少量の取り扱いが多いため、SKU登録数やシステム連携の有無によって費用が変動します。
小規模事業者向けには初期費用が無料のプランを提供している会社もありますが、安定稼働には一定の投資が必要です。
特にECモールやカートシステムと倉庫をAPIで連携する場合、設定費用が追加されることもあります。
長期的には、初期設定を丁寧に行うことで在庫差異の削減や出荷精度の向上につながり、トラブル回避の観点からも欠かせない費用です。
保管料
保管料の相場料金は1パレットあたり月3,000~5,000円程度、または1棚あたり月2,000~4,000円程度です。
保管料は、商品の在庫を倉庫に預ける際に発生する固定費です。
雑貨はサイズや形状が多岐にわたるため、パレット単位や棚単位で課金されるケースが一般的です。
小物雑貨は棚単位、大型雑貨はパレット単位の料金体系になることが多いです。
在庫量が増減しやすい業界では、効率的な配置や在庫圧縮でコスト削減が可能です。
ただし、繁忙期やシーズン商材では臨時追加スペース利用料がかかる場合もあります。
また、空調やセキュリティが必要な商品の場合、追加費用が発生する点も注意が必要です。
保管料は毎月の固定費になりやすいため、長期的なコスト管理の観点からも重要です。
入庫作業料
入庫作業料の相場料金は1件あたり200~500円程度、または1点あたり10~30円程度です。
入庫作業料は、仕入先やメーカーから納品された商品を倉庫に受け入れる際に発生します。
主な作業は数量検品、破損確認、ラベル貼付、仕分け、棚入れなどです。
雑貨は小物から大型商品まで幅広く、検品や仕分けの工数がかかる場合が多いため、費用が変動しやすいのが特徴です。
特に個包装やセット商品が多い場合は追加コストがかかります。
また、システム連動で入庫処理を行う場合は、スキャン作業やデータ登録費用が加算されることもあります。
入庫精度は後工程の出荷精度に直結するため、費用だけでなく品質の高さも確認すべきポイントです。
出荷作業料
出荷作業料の相場料金は1件あたり300~600円程度、または1点あたり20~50円程度です。
出荷作業料は、受注後に商品をピッキング・検品・梱包し、送り状を発行して出荷する際に発生する費用です。
雑貨は多品種少量で注文が入りやすく、1件あたりのピッキング点数が多くなる傾向があります。
壊れやすい雑貨やギフト対応が必要な商品は、丁寧な梱包や追加資材が必要となり、費用が高くなるケースもあります。
また、セールやイベント時には出荷件数が急増し、臨時費用が発生する場合もあります。
出荷作業料は利益率に直結するため、効率と品質を両立できる物流パートナー選びが重要です。
配送料
配送料の相場料金は60サイズで500~800円程度、100サイズで800~1,200円程度です。
配送料は、商品を顧客に届ける際に発生する変動費です。
サイズ・重量・配送エリアによって料金が異なり、物流代行会社を通じることで法人契約運賃を利用できるメリットもあります。
雑貨は商品サイズがバラバラなため、同梱・個別配送の判断でコストに大きな差が出ます。
また、スピード配送や日時指定、離島配送などのオプションでは追加費用が発生する場合もあります。
送料無料施策を行うECでは、販売戦略との兼ね合いから配送料の最適化が極めて重要です。
流通加工費(オプション)
流通加工費の相場料金は1件あたり50~300円程度です。
流通加工費は、通常の入出庫作業に追加して発生するオプション費用です。
代表例としてギフトラッピング、セット組み、のし掛け、シール貼付などがあります。
雑貨はギフト需要が多いため、こうした加工依頼が頻繁に発生します。
シンプルなラベル貼付は数十円程度ですが、複雑なラッピングやセット組みは数百円に達することもあります。
外注化により自社の人件費を削減できるメリットがある一方、品質管理を徹底することが重要です。
返品処理費
返品処理費の相場料金は1件あたり200~500円程度です。
返品処理費は、顧客から返品された商品の検品・再販可否の判断・在庫戻しなどで発生する費用です。
雑貨は破損リスクが比較的高いため、返品率も一定水準以上になる傾向があります。
内容によっては再包装や廃棄費用まで発生することもあります。
返品対応のスピードは顧客満足度に直結するため、コストだけでなく体制の充実度も確認すべきです。
また、返品理由の分析を行うことで不良率改善や在庫精度向上に役立ち、長期的にはコスト削減につながります。
システム利用料
システム利用料の相場料金は月額5,000~50,000円程度です。
システム利用料は、在庫管理や受注処理を行うWMS(倉庫管理システム)や、ECモール連携システムの利用にかかる費用です。
小規模事業者は月額数千円で利用できるケースもありますが、大規模ECや多モール連携では数万円規模になることもあります。
雑貨はSKU数が多く在庫管理が複雑になりやすいため、システム活用が不可欠です。
リアルタイム反映や自動受注取り込み機能によりヒューマンエラー削減が可能となります。
さらに、分析機能を活用することで売上予測や在庫最適化にも貢献します。
毎月の固定費ではありますが、効率化によるコスト削減効果を考えれば積極的に導入すべき項目です。
雑貨物流代行を利用するメリット
外部の専門性を活用することで、在庫や出荷の精度向上からコストの最適化まで多面的な効果が期待できます。まずは代表的なメリットを整理し、自社にとってのインパクトを具体化していきます。
在庫管理の効率化
雑貨は種類やサイズが多岐にわたり、SKU数が膨大になりやすい商材です。物流代行を利用することで、倉庫管理システム(WMS)を駆使した正確な在庫管理が可能となり、欠品や過剰在庫のリスクを最小限に抑えられます。
さらに、在庫状況をリアルタイムで把握できるため、販売戦略や発注計画を柔軟に立てることができます。
これにより、売上機会を逃さず、無駄なコストを削減し、安定したEC運営や小売事業の基盤を築くことにつながります。
在庫管理を強化することで、事業全体の安定性が高まります。
出荷スピードの向上
雑貨の販売では顧客がスピーディーな配送を期待するケースが多く、物流代行を活用することでそのニーズに応えられます。
専門業者は効率的なピッキング・梱包フローを整備しているため、自社で行うよりも短時間で出荷が完了します。
また、繁忙期やセール時期でも臨機応変に対応可能なキャパシティを持っており、出荷遅延による顧客満足度の低下を防げます。
スムーズな配送は顧客体験を向上させ、リピート購入や口コミによる新規顧客獲得にもつながります。
配送スピードの速さは顧客満足度に直結します。
保管スペースの削減
雑貨は形や大きさがさまざまで、自社倉庫やオフィスを圧迫しやすいのが特徴です。物流代行を利用すれば、商品ごとに最適な保管方法で効率よく在庫を管理でき、自社スペースを有効活用できます。
特に成長期のEC事業者にとって、事務所や店舗のスペースを商品で埋めてしまうリスクを回避できるのは大きなメリットです。
さらに、倉庫業者は温度・湿度管理やセキュリティ対策を整えているため、商品を安全に保管できる環境が整っています。
保管スペースの削減はコスト削減にもつながります。
流通加工サービスの活用
雑貨はセット組み、ラッピング、ラベル貼りなどの付加作業が求められるケースが多くあります。物流代行ではこうした流通加工サービスを一括して任せられるため、社内の作業負担を大幅に軽減できます。
キャンペーンや季節イベントに合わせたパッケージングもスムーズに対応でき、販売戦略に柔軟性を持たせることが可能です。
このように流通加工を外部に任せることで、社内リソースをコア業務に集中させることができます。
流通加工を外部に任せれば、本業に集中できます。
コストの最適化
物流代行を利用することで、固定費を変動費に置き換えられる点も大きな利点です。出荷量に応じてコストが変動するため、繁忙期と閑散期で効率的に資金を運用できます。
また、物流業者は複数のクライアントの荷物をまとめることで配送コストを抑えるため、自社単独で契約するよりも有利な運賃条件を得られる場合があります。
結果として、利益率を確保しながらも顧客に適正価格で商品を提供できる体制を築くことが可能となります。
コストの最適化は利益率アップに直結します。
雑貨物流代行を利用するデメリット
一方で、委託に伴うリスクや社内ナレッジの希薄化など、留意すべき点も存在します。ここでは想定しやすいデメリットを把握し、回避や軽減のための考え方へとつなげます。
自社ノウハウの蓄積が難しい
物流業務を外部に委託することで、自社に物流ノウハウが蓄積しにくいという課題があります。
在庫管理や配送フローをすべて委託すると、社内で改善や効率化を図る力が弱まる可能性があります。
特に、急成長期や新たなビジネスモデルに挑戦する際には、自社内に物流知識がないことで意思決定が遅れるリスクもあります。
外注先との連携を強めると同時に、最低限の物流知識は社内に残す工夫が必要です。
すべてを委託すると、自社に物流スキルが残らない点に注意が必要です。
コストが割高になる場合がある
物流代行を利用すれば効率化は図れますが、必ずしもコストが下がるとは限りません。
小規模な事業や取扱量が少ない場合は、代行会社の料金体系が割高になるケースもあります。
さらに、特殊な梱包や流通加工を多用すると、追加費用が積み重なり予算を圧迫することもあります。
導入前に、コストシミュレーションを行い、固定費・変動費のバランスを確認しておくことが大切です。
取扱量が少ない場合は、むしろコスト増になることもあります。
委託先依存のリスク
物流代行に頼りすぎると、委託先の対応力に依存するリスクが高まります。
繁忙期や急な需要変動に対応できない業者を選んでしまうと、出荷遅延や顧客クレームにつながります。
また、システム障害や業者側の経営不安定化が起こった場合、自社の事業も大きく影響を受けてしまいます。
リスクを分散するためには、複数の物流会社を比較・検討し、委託先の実績や対応力を事前に確認することが重要です。
委託先に依存しすぎると、トラブル時に自社も巻き込まれます。
情報共有の手間が増える
物流代行を利用すると、社内と委託先との情報連携が欠かせないため、コミュニケーションの手間が発生します。
例えば、在庫数・出荷状況・返品情報などを正確に共有しないと、販売現場で混乱を招く可能性があります。
特に、多品種少量を扱う雑貨では情報更新の頻度が高いため、連携体制の構築がスムーズに行えるかどうかがポイントです。
情報共有がスムーズにいかないと、現場でトラブルにつながります。
自社方針とのズレが生じる可能性
物流代行会社は複数の企業を担当しているため、自社の方針やブランドイメージと完全に一致した対応が難しいこともあります。
特に雑貨は梱包やラッピングなどでブランド体験を演出することが多いため、委託先の対応が顧客体験に影響するリスクがあります。
このため、導入前に梱包ルール・配送ポリシーを明確化し、委託先に共有することが重要です。
ブランド体験を重視する場合は、委託先の対応方針を必ず確認しましょう。
まとめ
雑貨の物流代行は、商品特性や販売戦略に合わせた運用設計が成功の鍵となります。特徴と選び方、費用構造、メリットとデメリットを踏まえ、自社に最適なパートナーとスキームを構築しましょう。具体的な要件が固まっていれば、候補企業へのヒアリング項目を洗い出し、試験運用で検証を進めるのがおすすめです。