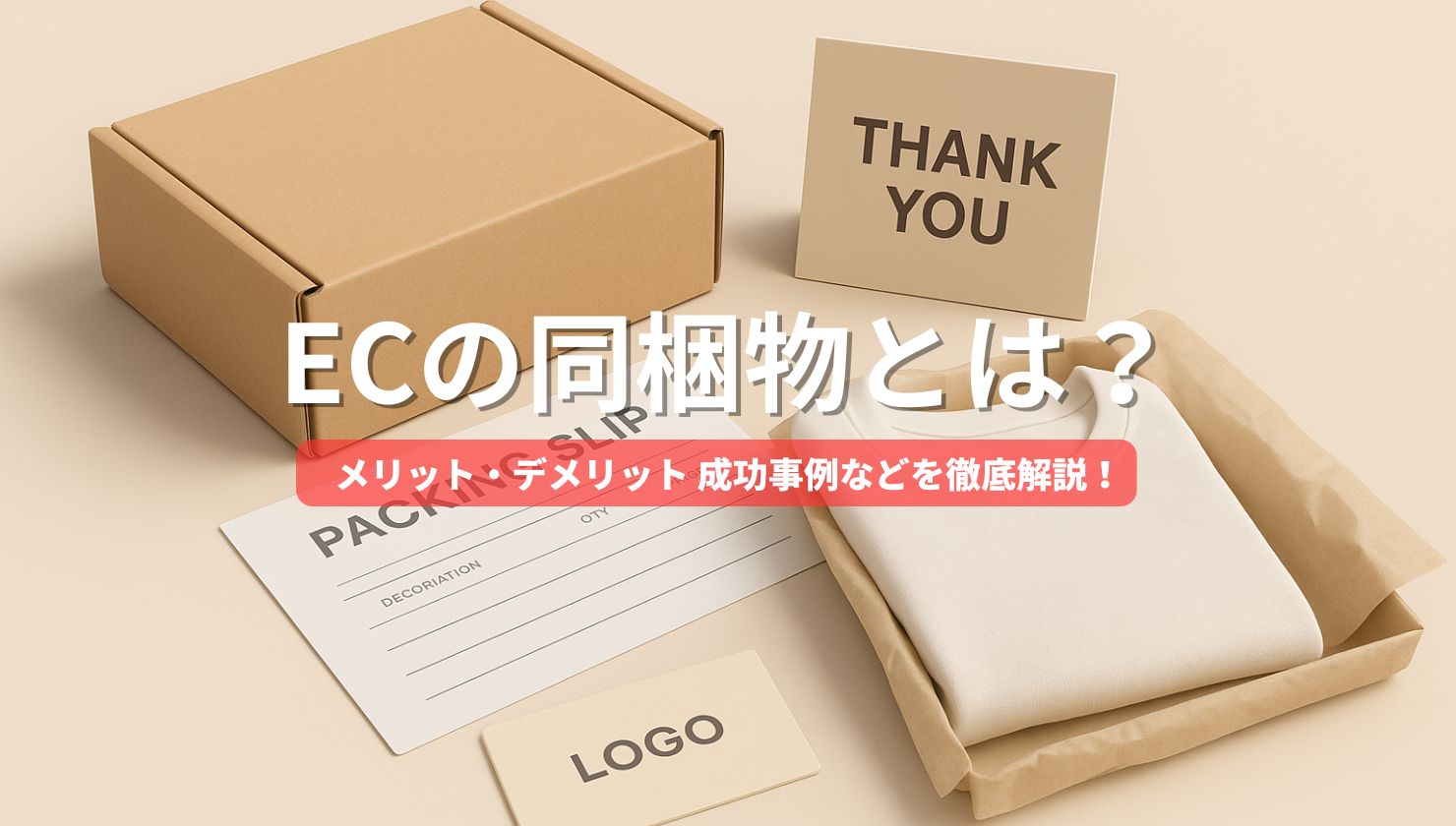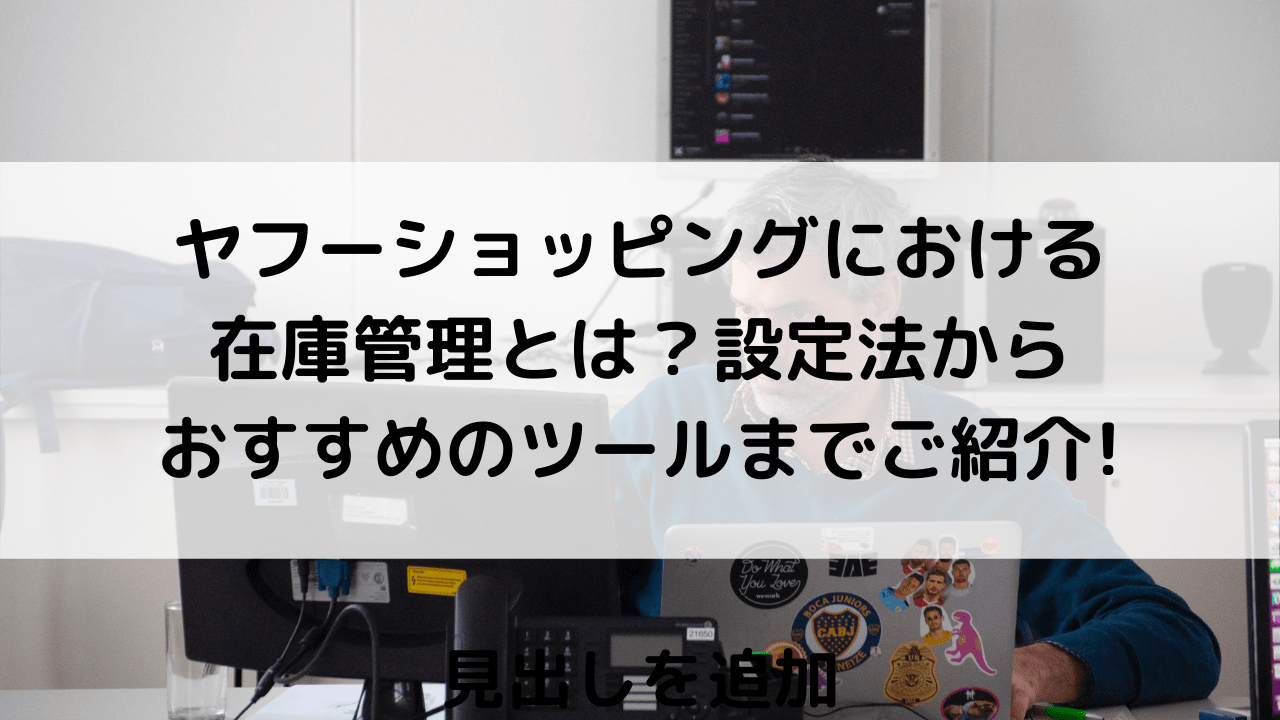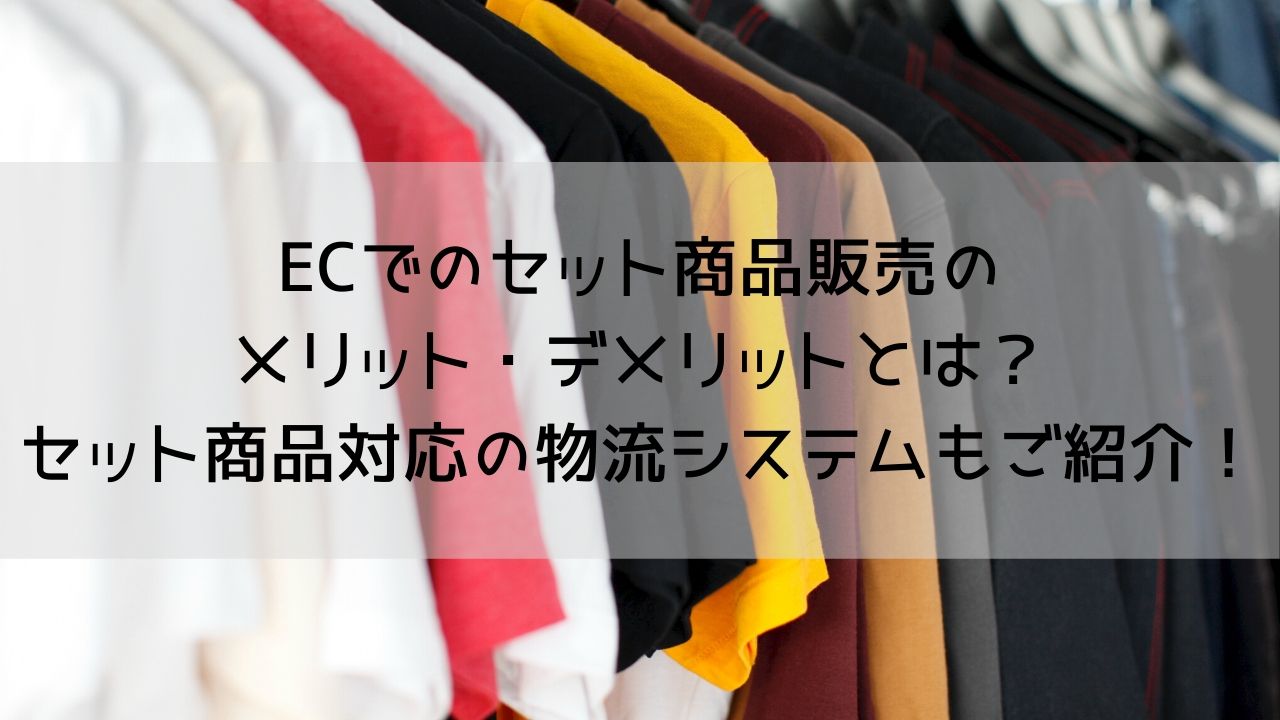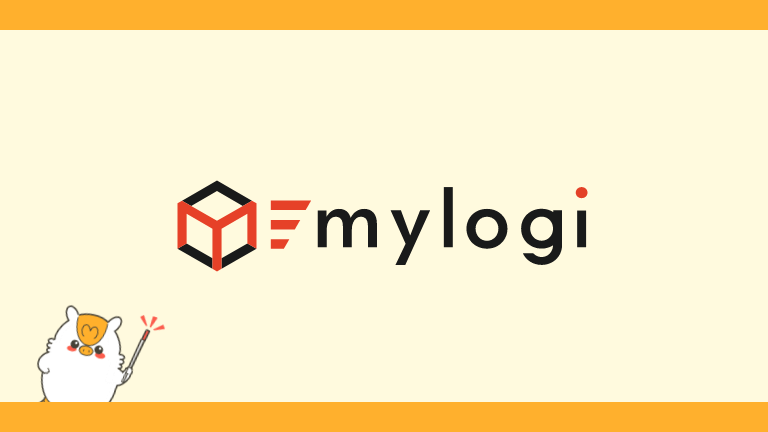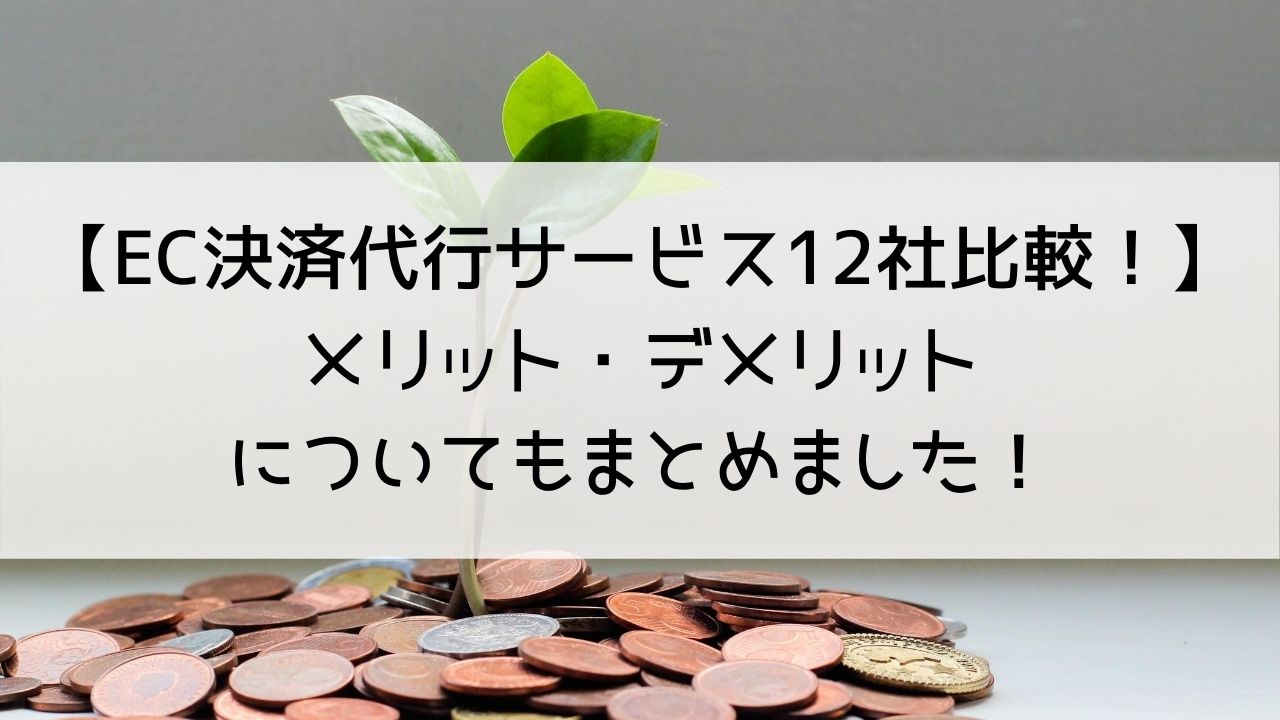ECの同梱物とは?同梱物を入れるポイントは?と気になっていませんか。
ECの同梱物とは、ネット通販で商品を発送する際に一緒に同封される印刷物やサンプル、ノベルティなどのことです。
またECの同梱物を決める際は、下記のポイントを確認するようにしましょう。
▼ECの同梱物を決める際のポイント
- ・ターゲット顧客を明確にする
- ・商品の特性に合わせる
- ・目的を明確にして測定できる形にする
- ・ブランドメッセージと統一感を持たせる
- ・顧客の体験価値を高める
- ・コストと管理負担も加味する
この記事では、リピート促進やブランド認知UP、クロスセル・アップセル、レビュー促進などの目的ごとにおすすめのEC同梱物について詳しく解説していきます。
是非参考にしてくださいね。
ECの同梱物とは?
ECの同梱物とは、ネット通販で商品を発送する際に一緒に同封される印刷物やサンプル、ノベルティなどを指します。
単なる「おまけ」ではなく、顧客とのコミュニケーションを深めたり、リピート購入やファン化を促進したりする重要な役割を持っています。
例えば、クーポンや試供品を入れることで「また買いたい」と思わせたり、ブランドストーリーやサンクスメッセージを同梱することで信頼感を高めたりすることができます。
同梱物は、ECにおける「顔が見えない取引」に温かみを与え、顧客体験を豊かにするための大切な施策なのです。
ECで同梱物を入れるメリット
同梱物を入れるメリットは、単なる販促効果にとどまりません。
リピート購入を促したり、顧客との信頼関係を強めたり、ブランドイメージを向上させたりと、多方面でプラスの影響を与えます。
特に、顧客が商品を受け取るタイミングは購買意欲や満足度が高まっている瞬間であり、その状態で適切な情報や特典を届けることで行動につながりやすくなります。
次から詳しい内容を見ていきましょう。
リピート購入のきっかけを作れる
ECで同梱物を入れるメリットのひとつとして リピート購入のきっかけを作れるということがあげられます。
これは、同梱物を活用して「次回も買いたい」と思ってもらう導線を作るということです。
ECでは一度きりの購入で終わってしまうケースも多いため、リピーターを育てることは売上の安定化に直結します。そこで効果的なのが「次回購入時に使えるクーポン」や「サンプル商品の同封」です。
たとえば・・
- ・500円OFFクーポンを同梱
- ・同シリーズの別フレーバーの試供品
- ・「次回購入で●%オフ」などのカード
- ・ポイントアップの案内や特典の告知
など。これらを同梱することで、顧客の頭の中に「また買う理由」をつくることができます。
また、商品を実際に使っているタイミングで届く情報なので、メールやSNS広告よりも印象に残りやすく、購買行動につながりやすいのが特徴です。
「初回購入で満足→次もお得に試せる→リピーター化」という流れを自然につくれるのが、同梱物の大きな強みです。
顧客との信頼関係を深められる
ECで同梱物を入れるメリットとして、「顧客との信頼関係を深められる」ということがあげられます。
というのも、ネット通販は顔の見えない取引のため、店舗での接客のような「人の温かみ」が感じられにくい傾向があります。
そんな中、同梱物は顧客との信頼関係を築くための大きな武器になります。とくに「丁寧な気遣い」や「感謝の気持ち」が伝わる内容は、顧客に好印象を与えやすいです。
たとえば以下のような工夫が効果的です。
- ・手書き風のサンクスメッセージ
- ・「ご購入ありがとうございます」といった一言メモ
- ・梱包担当者の名前入りカード
- ・商品を丁寧に扱っていることがわかる梱包説明書
こうした同梱物は、ただ商品が届くだけでなく「人が心を込めて届けてくれた」と感じさせる力があります。
結果として、商品やショップへの安心感・信頼感が高まり、リピートや口コミにつながりやすくなります。
一度の購入を「良い体験」に変えることで、長期的な関係づくりのきっかけになるのです。
ブランドイメージの向上
ECで同梱物を入れるメリットとして、「ブランドイメージの向上」ということがあげられます。
オンラインでの買い物はどうしても価格や機能といったスペック勝負になりやすく、ブランドの「世界観」や「ストーリー」を伝えにくい面があります。
そんな中で同梱物は、ブランドらしさを直感的に伝えるための大切なタッチポイントになります。視覚的なデザインや言葉選びによって、他社とは違う価値観や美意識を印象づけることができます。
たとえば以下のような工夫が効果的です。
- ・ブランドカラーやロゴを使ったオリジナル封筒やカード
- ・商品の背景や開発ストーリーを紹介するミニ冊子
- ・ブランドの理念やコンセプトを語るリーフレット
- ・SNSでの発信を促すハッシュタグ付きカード
こうした同梱物は、「このブランド、なんかいいな」と感覚的に伝わるきっかけになります。
結果として、単なるモノ売りではなく、「共感されるブランド」として印象づけることができ、ファン化やSNSでの拡散にもつながります。
ブランドの世界観を伝えることで、価格や商品力だけに頼らない“選ばれる理由”が生まれるのです。
クロスセル・アップセルのチャンス
ECで同梱物を入れるメリットとして、「クロスセル・アップセルのチャンスが生まれる」ということがあげられます。
ネットショップでは関連商品や上位商品の提案をしても、ページを閉じた瞬間に忘れられてしまうことが少なくありません。
そんな中、同梱物は実際に商品が届いた“タイミング”で直接アプローチできる貴重な手段になります。購買のモチベーションが高まっている状態で、次の商品提案をすることで、より高い確率で興味を持ってもらえるのです。
たとえば以下のような工夫が効果的です。
- ・現在の商品と相性のいいアイテムの紹介チラシ
- ・上位グレードの商品の比較案内
- ・「まとめ買いでお得」などのセット提案
- ・顧客の購買傾向に合わせたカテゴリ別カタログ
こうした同梱物は、店舗側が“次に買ってほしい商品”を自然な形で提案できるツールとして機能します。
結果として、顧客単価の向上や新商品の認知促進にもつながります。
「ただの購入」で終わらせず、次の一手につなげる。それが同梱物の強みなのです。
クレーム・返品を減らす
ECで同梱物を入れるメリットとして、「クレーム・返品を減らす」ということがあげられます。
ネット通販では実物を見られない分、顧客との間に“認識のズレ”が生まれやすく、それが不満や返品につながってしまうことがあります。
そんな中、同梱物は「正しい使い方」や「注意点」「サポート案内」を伝える役割を果たすことができます。特に初めて使う商品や、使用にコツがいるアイテムにおいては、事前の丁寧なフォローがクレーム防止に大きく貢献します。
たとえば以下のような工夫が効果的です。
- ・使い方を写真付きで説明したリーフレット
- ・よくある質問とその答えをまとめたQ&Aシート
- ・商品の取り扱いに関する注意事項の案内
- ・問い合わせ窓口やサポート対応の連絡先カード
こうした同梱物は、「トラブルを未然に防ぐ」ためのガイドとして働きます。
結果として、顧客満足度の向上だけでなく、店舗側の対応負担の軽減にもつながります。
「しっかり配慮されている」と感じてもらうことで、安心して購入してもらえる環境を整えることができるのです。
ECで同梱物を入れるデメリット
同梱物には多くのメリットがありますが、一方で注意すべきデメリットも存在します。
たとえば、印刷費や梱包作業によるコスト増加、在庫や管理の手間、そして内容によってはゴミ扱いされるリスクやブランドイメージを損なう可能性があります。
さらに、Web広告のように効果測定が容易ではないため、成果を数値化しにくいという課題もあります。
次から詳しい内容を見ていきましょう。
コストがかかる
ECで同梱物を入れる場合、見落としがちなコストが複数発生します。これは単なる印刷費用だけでなく、梱包作業や物流全体にまで影響を及ぼす可能性があります。
- 印刷・制作費:サンキューカードやチラシ、クーポンなどの印刷・デザインコスト
- 作業工数:同梱物を追加することで、梱包時間が増え人件費が上昇
- 物流コスト:同梱物によってサイズや重量が増し、送料が上がる場合も
たとえば、商品1点だけであればクリックポストで発送できるものが、同梱物を加えることで宅配便に変更せざるを得ないケースもあり、送料が一気に跳ね上がることもあります。
さらに、定期的に同梱物の内容を見直さないと、「効果のない施策に無駄なコストをかけ続けてしまう」という事態に陥ることもあります。
ゴミ扱いされるリスクがある
ECで商品に同梱物を入れる際、「せっかくコストをかけて用意したのに、開封直後にゴミとして処分される」というケースが少なくありません。これは、ユーザーが「広告チラシ」「不要な紙モノ」「ノベルティ」などを、購買体験に不要なものと判断してしまうためです。
このような「ゴミ認定」される同梱物には、以下のような特徴があります。
- ・商品の内容や用途と関係のない宣伝物
- ・紙質やデザインが安っぽく、読みたくならない
- ・情報量が多く、読む気にならない長文の案内
- ・一見してキャンペーンの押し売り感がある
ユーザーにとって、ネットショッピングは「最短でモノを受け取る手段」であり、それ以外の要素は煩わしく感じることもあります。
また、ゴミ扱いされてしまうと単に無駄になるだけでなく、「このショップはムダが多い」「エコじゃない」といったマイナスイメージを持たれるリスクも。環境意識が高い顧客層であれば、リピート率にも影響が出る可能性があります。
同梱物を活用する際は、「ユーザーが本当に喜ぶか?」という視点で見直すことが重要です。
不要な紙の配布ではなく、実用性や価値のあるコンテンツとして設計することで、ゴミ扱いされるリスクを下げることができます。
内容が適切でないとブランドイメージを下げる
同梱物は、購入後の体験にプラスの印象を与えるチャンスである一方、内容が適切でない場合は逆効果になり、ブランドイメージを損なうリスクがあります。
たとえば、以下のようなケースが該当します。
- ・世界観やトンマナが商品と合っていない広告やチラシ
- ・安売り感の強いクーポンや次回購入の押し売り
- ・誤字脱字、印刷の粗さ、レイアウトの乱れなど制作の品質が低い
- ・ターゲットに合っていない内容や言葉遣い
たとえば、高級感を打ち出しているブランドが、派手な色使いや安価なチラシを同梱してしまうと、ユーザーの期待とのギャップが生まれ、ブランドに対する信頼が揺らぎます。
また、ノベルティやメッセージカードの内容が雑だったり、使い回し感があったりすると、「自分に向けたものではない」と感じられ、かえって印象が悪くなります。
ユーザーは商品と一緒に届いた同梱物を通じて、「このショップはどんな会社なのか」「どれだけお客様を大切にしているか」などを無意識に判断します。
そのため、同梱物をつくる際は「この内容はブランドの価値観と合っているか?」「ユーザーにとって意味があるか?」という視点で、設計・デザイン・表現すべてにこだわる必要があります。
同梱物は小さな紙一枚でも、ブランドの“声”として届く大事な要素。内容が適切でないと、期待を裏切り、信頼を損なうことにつながります。
在庫・管理の手間が増える
ECで同梱物を導入する際、見落とされがちなのが「在庫管理や運用オペレーションへの影響」です。商品以外に配布物が増えるということは、それだけで管理業務が煩雑になり、現場に負荷をかける要因となります。
具体的には、以下のような手間が発生します。
- ・同梱物の在庫を別途管理する必要がある
- ・商品と同梱物をセットにする工程が増える
- ・複数の同梱パターンがある場合、ピッキングや梱包時の間違いリスクが上がる
- ・季節キャンペーンや内容変更があるたびに指示・教育が必要
たとえば、リピート促進用のチラシを商品と一緒に封入する場合、商品のSKUとは別に「同梱物の在庫数」もリアルタイムで把握しておかなければなりません。在庫切れに気づかず出荷してしまうと、本来伝えたかった情報が届かず、施策が無駄になる可能性も。
また、現場のオペレーションが増えることで、梱包ミスや出荷遅延といったトラブルも発生しやすくなります。とくに、人手が限られている中小規模のECでは、日々の業務への負担が無視できません。
同梱物の導入は、売上やブランド体験の向上に寄与する一方で、運用面の設計を誤ると現場が疲弊し、本来の業務品質まで落としてしまうリスクがあります。
導入時は、商品在庫と同様に同梱物の在庫管理・封入フロー・人員体制などをあらかじめ設計しておくことが重要です。
効果測定がしにくい
同梱物は、リピート促進やブランド認知向上などを目的として使われることが多い施策ですが、その効果を正確に測定するのが難しいという課題があります。これが、EC運営者にとって見過ごせないデメリットの一つです。
たとえば、購入者に次回使えるクーポンをチラシで同梱したとしても、それを使ったかどうかがシステム上で紐付けられていなければ、「何枚配ったうち、どれだけ利用されたか」が把握できません。結果的に、費用対効果の判断が曖昧になります。
よくある測定しにくいパターンとして、以下のようなケースがあります。
- ・クーポンや案内に個別のコードが設定されていない
- ・複数の施策を同時に実施しているため、どの施策の効果か切り分けできない
- ・そもそもお客様が同梱物を見ていない可能性がある
- ・リピート購入までの期間が長く、同梱物の影響かどうか追いづらい
また、Web広告やメルマガと異なり、クリック率や閲覧時間といった定量的なデータが取得できないのも大きなネックです。A/Bテストも実施しづらく、運用改善のPDCAが回しにくくなります。
そのため、同梱物を戦略的に活用するには、クーポンコードの発行・アンケート連携・LTV分析など、オフライン施策の中でも「データ化できる仕組み」を整えることが重要です。
効果が見えづらいままなんとなく続けてしまうと、コストばかりがかかり、運用リソースも消耗してしまいます。成果が可視化できる工夫をしながら、目的に合った形で同梱物を設計していくことが求められます。詳しい効果測定の方法はこちらから!
ECの同梱物を決める際のポイント
同梱物は「何を入れるか」以上に、「どのような目的で、どんな顧客に届けるか」が重要です。
闇雲にアイテムを追加しても効果は出にくく、逆にコストや手間ばかりが増えてしまうこともあります。
ターゲットや商品の特性、ブランドメッセージとの一貫性を意識しながら設計することで、同梱物は単なる販促物ではなく、顧客体験を高める強力な武器となります。
また、コストや管理負担も考慮し、測定可能な仕組みを組み込むことで、持続的に運用できる施策へと育てることが可能です。
次から詳しい内容を見ていきましょう。
ターゲット顧客を明確にする
ECの同梱物を考える際、「どんな人が商品を購入しているのか」をしっかり把握することが第一歩です。
届ける相手のニーズや関心に合った内容でなければ、どんなに凝った同梱物も開封されずに捨てられてしまう可能性がありますが、同梱物のターゲットを明確にすることで、まず開封率や閲覧率が高まり、手に取ってもらえる確率が大きく上がります。
▼顧客タイプ別|おすすめの同梱物例
| 顧客タイプ | 特徴 | おすすめの同梱物 |
|---|---|---|
| 20代女性(美容系) | 感性重視、SNS利用が活発 | サンプル・おしゃれなメッセージカード・SNS投稿特典 |
| 30〜40代主婦(日用品) | 実用性重視、リピート傾向あり | 再注文クーポン・便利な使い方ガイド・チラシ |
| 40代以上の男性(趣味・ツール) | 商品理解を重視、コスパ重視 | 製品スペックの詳細資料・次回割引案内・ブランド紹介 |
| 初回購入者 | ECに対する不安がある | 感謝メッセージ・会社紹介・お試し商品・サポート案内 |
| リピーター | 信頼関係が構築されている | VIP特典・限定クーポン・新商品の案内 |
同梱物の効果を最大限に引き出すには、まず「誰に届けるか」を明確にすることが不可欠です。
顧客の属性や購買傾向を分析し、それぞれに合った内容を用意することで、開封率や反応率が格段に向上します。
特に、初回購入者とリピーターでは期待している情報が異なるため、同じ内容を一律で入れるのではなく、関係性に応じて出し分ける工夫が大切です。
「自分のために用意された」と感じてもらえる同梱物は、ECにおける無機質な取引に温かみを与え、顧客とのつながりを深める強力な接点になります。
商品の特性に合わせる
ECの同梱物を企画する際には、「どんな商品を販売しているのか」を踏まえて内容を設計することが重要です。
商品ジャンルや価格帯、利用シーンなどにより、顧客が求める情報や期待する体験は大きく異なります。
たとえターゲットが明確でも、商品との関連性が薄い同梱物では関心を持たれず、印象にも残りません。
商品の特性にマッチした同梱物は、活用率・満足度ともに高まり、ブランド理解やリピート購入を自然と促してくれます。
▼商品ジャンル別|おすすめの同梱物例
| 商品ジャンル | 特徴 | おすすめの同梱物 |
|---|---|---|
| 食品・飲料 | 消費が早く、頻度高く使われる | レシピカード・次回割引クーポン・保存方法の案内 |
| アパレル・ファッション雑貨 | 季節感やコーディネートが重要 | 着こなし提案・スタイリング冊子・次シーズンの新作情報 |
| コスメ・美容グッズ | 使用感・相性が気になる | ミニサイズのサンプル・成分解説カード・使い方ガイド |
| 家電・ガジェット | 機能の理解や設定が必要 | セットアップマニュアル・FAQ冊子・長期保証の案内 |
| キッズ・ベビー用品 | 安全性・信頼感が重視される | 素材のこだわり解説・お手入れ方法・使用年齢の目安表 |
商品の魅力を引き出す同梱物は、販売後の満足度を高めるだけでなく、顧客の「このお店、分かってるな」という共感にもつながります。
単なる販促ツールとしてではなく、「購入体験の延長」として考えることが、長期的なブランド育成につながるポイントです。
目的を明確にして測定できる形にする
ECにおける同梱物は、「ただ入れるだけ」では意味がありません。
大切なのは「何のために同梱するのか」という目的を明確にし、その効果をきちんと測定できる形にしておくことです。
たとえば「リピート購入を促したい」「SNSでの拡散を狙いたい」「レビューを増やしたい」など、目的によって同梱物の内容や導線設計は大きく変わります。
目指すゴールが曖昧なままだと、ただコストや手間がかかるばかりで、改善のヒントも得られません。
効果測定ができれば、ABテストや改善にもつなげやすく、PDCAを回しながらより成果の出る施策へと育てることが可能です。
▼目的別|おすすめの同梱物と測定方法
| 目的 | おすすめの同梱物 | 測定方法 |
|---|---|---|
| リピート購入を増やす | 次回購入で使えるクーポン | クーポンコードの利用数を計測 |
| SNSでの拡散を促す | ハッシュタグ付き投稿カード | 指定ハッシュタグの投稿数を集計 |
| レビュー数を増やす | レビュー投稿で特典がもらえる案内 | レビュー件数の増加をモニタリング |
| ブランドのファンを増やす | ブランドストーリーや想いを伝える冊子 | アンケートでブランド理解度を調査 |
| クロスセル(関連商品訴求) | おすすめ商品のカタログ | 記載URLやQR経由のアクセス数を分析 |
・ECのリピート促進のためによく使われる同梱物
・ECのブランド認知・ファン化のためによく使われる同梱物
・ECのクロスセル・アップセルのためによく使われる同梱物
・ECのレビュー促進のためによく使われる同梱物
“効果が見えない”施策は、改善も評価もできません。
同梱物を通じて何を達成したいのか、その目的を明確にしたうえで、数字で結果が追えるような仕掛けを組み込んでおくことが、持続可能な施策の鍵となります。
ブランドメッセージと統一感を持たせる
ECの同梱物を企画する際、「ブランドの世界観や伝えたい価値観」と一致しているかを意識することが大切です。
いくら内容が豪華でも、デザインや言葉遣いがブランドイメージとズレていると、顧客に違和感を与えてしまい、信頼や印象に悪影響を及ぼすことがあります。
一貫性のあるメッセージやビジュアルを保つことで、ブランド全体の認知力や共感が高まり、記憶にも残りやすくなります。
たとえば、ナチュラル志向のスキンケアブランドなら、同梱物もナチュラルカラーや手書き風フォント、再生紙を使ったリーフレットなど「世界観を壊さない工夫」が求められます。
逆に、テクノロジー系のガジェットブランドであれば、スタイリッシュなデザインやシンプルな構成がマッチします。
▼ブランドタイプ別|統一感を出すための同梱物設計
| ブランドタイプ | 世界観・特徴 | 同梱物で意識したいポイント |
|---|---|---|
| ナチュラル・オーガニック系 | 自然志向・やさしさ・エシカル | 再生紙・やわらかい色味・手書き風の文章 |
| 高級・プレミアム系 | 上質感・落ち着き・信頼 | 厚手の用紙・箔押し加工・丁寧な言葉遣い |
| ファミリー・キッズ向け | 親しみやすさ・安心感・カラフル | イラスト入り・明るい色・親子向けのメッセージ |
| テクノロジー・デジタル系 | 機能性・シンプル・洗練 | 無駄のない構成・グレーや黒基調・論理的な説明 |
| カルチャー・個性派系 | ユニーク・表現重視・共感型 | 遊び心あるデザイン・キャッチーなコピー・世界観に合う印刷物 |
ブランドとして伝えたい「想い」や「空気感」が、商品だけでなく同梱物にも通っていることで、顧客の中に一貫した印象が形成されます。
一つひとつの表現やデザインが、顧客との信頼を築く「積み重ね」になると考えて設計しましょう。
顧客の体験価値を高める
ECの同梱物を設計するうえで大切なのは、「商品を受け取った瞬間から始まる顧客の体験」を豊かにすることです。
ただ商品が届くだけではなく、「想像以上の何か」があれば、感動や驚きが生まれ、そのブランド体験は強く記憶に残ります。
こうした体験価値は、SNSでのシェアやリピート購入、ポジティブな口コミにもつながる大きな力を持っています。
開封時のちょっとした驚きや喜びが、ECという無機質なやりとりに“温度”を与え、ブランドへの愛着を深めてくれます。
だからこそ、機能的な情報だけでなく、感情に訴える要素を同梱物に取り入れることが重要です。
▼体験価値を高める|同梱物の工夫アイデア
| 工夫の種類 | 具体例 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 感謝の気持ちを伝える | 手書き風メッセージカード・お礼のことば | 信頼・親近感の向上 |
| ちょっとしたサプライズ | ミニプレゼント・おまけの試供品 | 「得した感」や嬉しい驚きを提供 |
| 商品とのつながりを深める | 使い方ブック・おすすめ活用シーン紹介 | 商品の理解促進・活用率アップ |
| ワクワク感の演出 | 開封体験を楽しめる包装・QR付き動画メッセージ | SNSシェアの促進・ブランド認知拡大 |
| 次回の楽しみを演出 | 次回使えるクーポン・限定オファー | リピート購入の後押し |
“モノを売る”から“体験を届ける”へ。同梱物はその第一歩となる重要な接点です。
「このブランドからまた買いたい」と思ってもらえるような、心を動かす仕掛けを意識して設計していきましょう。
コストと管理負担も加味する
ECの同梱物を検討する際には、「効果があるかどうか」だけでなく、コストと管理の手間もしっかり考慮することが重要です。
見栄えのよいパンフレットや豪華なサンプルを入れれば、顧客満足度は高まりやすいかもしれません。
しかし、継続的に実施するには、印刷費・人件費・在庫管理などの負担も無視できません。
同梱物は「販促ツール」であると同時に、「運営フローに組み込まれる作業」でもあります。
無理なく回せる体制や予算の中で最大限の成果を出せるよう、費用対効果を意識した設計が求められます。
▼同梱物コスト・管理負担のチェックポイント
| 項目 | 確認すべき内容 | 対策・工夫例 |
|---|---|---|
| 印刷・制作コスト | フルカラー/特殊加工は高くなりやすい | 簡易なモノクロ印刷やまとめ発注で単価を抑える |
| 封入・仕分け作業 | 人手が必要/ミスが発生しやすい | 商品とセットで管理・仕分けの自動化を検討 |
| 在庫スペース | チラシやサンプルの保管場所が必要 | 期間限定・数量限定にして保管リスクを軽減 |
| 更新の手間 | キャンペーンや季節に合わせて入れ替えが発生 | 長期使用できる汎用デザインを活用 |
| 費用対効果 | 成果が見えにくい場合も | クーポンコードやQRで反応を測定 |
「たくさん入れる=良い」ではなく、「少ないコストで最大の成果を出す」視点が大切です。
限られたリソースの中で運用するECでは、管理体制やコスト感に無理がない設計をすることで、継続的かつ効果的な同梱施策が実現できます。
ECのリピート促進のためによく使われる同梱物
リピート購入を促すための同梱物は、EC運営において非常に重要な役割を担います。
代表的なのは、次回購入を後押しするクーポンや割引チケット、商品を試してもらえるサンプル、商品情報や世界観を伝えるカタログなどです。
次から詳しい内容を見ていきましょう。
クーポン券・割引チケット
クーポン券や割引チケットは、ECのリピート購入を促すうえで非常に高い効果を発揮する同梱施策のひとつです。
購入直後の顧客は、商品への満足度が高ければ「また買いたい」という心理状態になりやすく、そのタイミングで次回に使えるクーポンを手にすると、行動に移すハードルが一気に下がります。とくに以下のようなケースで効果が出やすくなります。
- ・食品・消耗品・化粧品など、一定期間で使い切る商品
- ・リピート間隔が短く、月に1〜2回購入されやすい商品
- ・購入頻度がまだ定着していない新規顧客へのアプローチ
クーポン設計のポイント
効果的なクーポンを設計するには、単に「割引」を提供するだけでなく、活用される仕組みを組み込むことが重要です。
- ・使用期限を設けて緊急性を演出(例:30日以内に使用)
- ・条件付き割引で客単価を引き上げ(例:5,000円以上で500円引き)
- ・「あなただけ感」を強調する限定クーポンにする
- ・QRコードを印刷し、スマホからすぐアクセスできるようにする
- ・LINE・SNS登録と連携し、ファン化を促進
これらの工夫を組み合わせることで、クーポンの使用率を高め、継続的な購入へとつなげることができます。
実施時の注意点
クーポンは便利な反面、使い方を誤るとブランドの価値や利益に悪影響を与えるおそれがあります。
- ・クーポンの乱発で「割引がないと買わない」顧客を生まないように注意
- ・利益率を事前に計算し、割引が赤字につながらないようにする
- ・クーポン経由の購入率やLTVを分析して、施策の効果を測定する
「とりあえず割引」で配布するのではなく、顧客との関係性を深める手段として設計し、効果検証と改善を繰り返すことが成功の鍵となります。
サンプル・試供品
サンプルや試供品の同梱は、商品を実際に体験してもらうことで、次回購入への確度を高めるリピート促進施策のひとつです。
「気にはなっていたけどまだ買っていなかった」「使い心地がわからず迷っていた」といった潜在的ニーズにアプローチできるため、新商品の認知拡大やクロスセルにもつながります。とくに以下のような場面で効果を発揮します。
- ・シリーズ商品やライン展開のある化粧品・ヘアケア用品
- ・食べきりサイズの食品や飲料などの味を体感してもらいたい商品
- ・定期購入前に「お試し」が重要な商品(サプリ・健康食品など)
サンプル設計のポイント
サンプルは、単に「おまけ」として渡すのではなく、次の購入につながる導線を意識した設計が必要です。
- ・現品と同じブランド・シリーズで関連性のある商品を選ぶ
- ・パッケージや封筒に「今すぐお試しください」といったメッセージを添える
- ・QRコードや案内カードで、すぐに本品の購入ページに誘導する
- ・「試して気に入ったら次回●%OFF」といったクーポンとセットで渡す
- ・LINE登録やレビュー投稿で、本商品の特典をもらえる仕組みをつくる
商品体験から購入までの流れをできるだけスムーズに設計することで、サンプルの効果を最大化することができます。
実施時の注意点
サンプルの同梱は好感度の高い施策ですが、コストや管理の面での注意も必要です。
- ・サンプル原価や送料の増加が利益を圧迫しないよう、コスト試算を行う
- ・内容物が顧客にとって無関係な商品だと逆効果になることがある
- ・使用方法や注意事項を明記し、誤使用によるトラブルを避ける
- ・在庫や賞味期限の管理が複雑にならないよう、運用体制を整える
「無料だからいいだろう」と軽く扱わず、ユーザー体験の質を高める一手として丁寧に設計・管理することが、信頼とリピートにつながります。
冊子・カタログ
冊子やカタログは、ECでの商品購入時に「次に見てほしいもの」「知ってほしいこと」をまとめて届けられる、情報価値の高い同梱物です。
顧客が商品を手に取ったタイミングでブランドや商品の世界観を伝えることができ、次回購入への関心を高めたり、クロスセル・アップセルのきっかけをつくったりするのに役立ちます。とくに以下のようなケースで効果的です。
- ・ラインナップが多く、シリーズ展開されている商品(コスメ・アパレルなど)
- ・季節ごと・キャンペーンごとに商品内容が変わるショップ
- ・ブランドの背景や作り手の想いを伝えたいストーリードリブンな商材
冊子・カタログ設計のポイント
カタログや冊子を作る際は、「読みたくなる」「とっておきたくなる」内容にすることが重要です。
- ・商品の使い方や活用シーンを紹介するコンテンツを入れる
- ・新商品や限定商品を特集として掲載し、次回購入意欲を刺激する
- ・スタッフのコメントや開発ストーリーなど、ブランドに親しみを感じる要素を加える
- ・購入導線として、QRコードやクーポンを掲載する
- ・季刊誌やシリーズ化することで「次も読みたい」と思わせる
「商品案内+読み物」の形式にすることで、ただの広告ではなく“役立つ情報”として顧客の記憶に残りやすくなります。
実施時の注意点
冊子やカタログの同梱は情報提供力が高い一方で、制作・運用に一定のリソースがかかる点に注意が必要です。
- ・印刷コストや同梱作業の手間が負担にならないように設計する
- ・すべての顧客に一律で同じ内容を配るとミスマッチが起こる可能性がある
- ・デザインや内容が古くなると逆にブランドイメージを下げる
- ・内容が多すぎると読まれずに捨てられてしまう
継続的な情報発信やブランド価値の訴求を目指す場合に特に有効な施策なので、読みやすさ・タイミング・ターゲットとの相性を意識して作ることが大切です。
ランクアップ特典や会員制度の案内
ランクアップ特典や会員制度の案内は、「継続して買い続けるメリット」を明確に示すことで、リピート購入を促進する同梱施策のひとつです。
「次のランクまであと●円」「会員だけの限定特典」といった情報を伝えることで、顧客にとっての“特別な存在”という意識を育て、継続的な購入行動を後押しします。とくに以下のようなケースで効果が出やすくなります。
- ・LTVが重視されるリピート型EC(コスメ・健康食品・日用品など)
- ・会員ステージによって割引やプレゼントが変わる制度を導入している場合
- ・ロイヤルカスタマーを育てていきたいブランド
案内設計のポイント
リピート促進につなげるためには、「今、どんな状態で」「次に何をすれば」「どんなメリットがあるか」を明確に伝えることが重要です。
- ・現在の会員ランクや獲得ポイント数をわかりやすく記載
- ・次のランク達成までの条件(例:あと●円のお買い物でゴールド会員)を提示
- ・ランクアップ後の特典(割引率・限定商品・送料無料など)を具体的に説明
- ・QRコードでマイページや会員ページへすぐアクセスできる導線を設置
- ・限定クーポンや誕生日特典などの“今すぐ得られるメリット”を強調
「このブランドは、自分を大切にしてくれている」と感じさせる設計にすることで、顧客のロイヤリティと継続率が高まります。
実施時の注意点
ランク制度や会員特典の案内は、情報が複雑になりやすいため、伝え方に工夫が必要です。
- ・特典内容が分かりにくいと、読まれずに終わってしまう
- ・ランクの基準や有効期限が明確でないと不信感を生む可能性がある
- ・特典の過剰提供は利益を圧迫するため、設計段階で収益性を確認
- ・ランクダウンの通知や条件変更時は、トーンに配慮する必要がある
「お得だから続けたい」「次のステージを目指したい」と思わせる仕掛けを同梱物で提供することで、リピート購入の強力な後押しとなります。
ECのブランド認知・ファン化のためによく使われる同梱物
ブランド認知やファン化を目的とした同梱物は、顧客との長期的な関係構築に欠かせません。
ストーリーや想いを伝える冊子、SNSでシェアしたくなるノベルティ、温かみのあるサンクスカードなどは、顧客に「このブランドが好き」と感じてもらうきっかけになります。
次から詳しい内容を見ていきましょう。
ブランドストーリーブックレット
ブランドストーリーブックレットは、企業や商品の背景にある「想い」や「こだわり」を顧客に伝えるための冊子型同梱物です。
単なる商品説明にとどまらず、創業のきっかけや職人の声、原料へのこだわり、地域とのつながりなどを丁寧に綴ることで、共感や信頼を生み出し、ファン化を促進します。特に以下のようなケースで効果を発揮します。
- ・商品やサービスに物語性や哲学があるブランド
- ・丁寧な製造工程や人の手が加わるハンドメイド系商材
- ・リピーターやファンの獲得が重要なD2Cブランド
ブックレット設計のポイント
共感を呼び、ブランド価値を伝えるブックレットにするには、視覚的・感情的な訴求を意識した構成が重要です。
- ・写真を多用し、ものづくりの現場や表情を伝える
- ・「誰が」「なぜ」「どうやって」つくっているかをストーリー形式で紹介
- ・ブランドの世界観を感じられるトンマナ(語り口やデザイン)で統一
- ・読み終わったあとに「応援したくなる」ような余韻を残す
- ・他商品紹介やSNS・メルマガ登録への導線もさりげなく設ける
「知ることで好きになる」構造を意識し、商品と一緒にブランドへの愛着が育まれるような冊子に仕上げることがポイントです。
実施時の注意点
ブランドストーリーブックレットは感情に訴える強力なツールですが、その分表現や印刷物としての完成度が問われます。
- ・内容が自己満足に偏りすぎると読み飛ばされる
- ・印刷コストがかさむため、LTVとのバランスを考える
- ・トーンや世界観がECサイトや商品と統一されているかをチェックする
- ・使いまわしがきかない場合は、更新・管理コストも想定しておく
単なる「読み物」ではなく、ブランドと顧客の架け橋になる存在として、丁寧に設計・制作することがファン化のカギになります。
オリジナルステッカーやノベルティ
オリジナルステッカーやノベルティは、ECでの購入体験に“嬉しいサプライズ”を加えることで、ブランド認知やファン化を促進する同梱施策のひとつです。
実用的であったり、デザイン性が高かったりすると「捨てずに取っておこう」「SNSに投稿しよう」という行動を引き出せるため、商品とともにブランドを印象付けるきっかけになります。とくに以下のようなケースで効果を発揮します。
- ・世界観やビジュアルを重視するファッション・雑貨ブランド
- ・顧客のSNS投稿を増やしたいD2Cブランドやライフスタイル系商品
- ・子ども向け・ファミリー層向け商材で“おまけ”の価値が高い場合
ノベルティ設計のポイント
ブランドを好きになってもらうためには、もらって嬉しい・使いたくなる工夫が重要です。
- ・ブランドロゴやキャラクターをあしらった高品質なステッカーやグッズを用意
- ・サイズや形状は郵送や梱包時にかさばらない設計にする
- ・「数量限定」「季節限定」などレア感を演出する
- ・SNS投稿キャンペーンと連動し、シェアを促進
- ・商品の世界観に合うデザインで「飾りたくなる」「持ち歩きたくなる」ものにする
“ちょっとしたプレゼント”として印象づけられれば、商品の満足度だけでなくブランドへの愛着にもつながります。
実施時の注意点
ノベルティは好意的に受け取られる反面、設計を誤ると逆効果になることもあります。
- ・品質が低いと「チープな印象」や「ゴミ扱い」されるリスクがある
- ・単価や送料の影響で、想定よりもコストがかさむことがある
- ・すべてのユーザーに響くとは限らないため、ターゲットとの親和性を重視する
- ・キャンペーン終了後などで使いまわすとブランド整合性が崩れる
「誰かに見せたくなる」「とっておきたくなる」ノベルティを作ることが、ブランド認知の拡大やファン育成に大きく貢献します。
手書き風のサンクスカード
手書き風のサンクスカードは、デジタルでは得られない「温もり」や「人の気配」を感じさせることで、ブランドへの親近感や信頼感を育む同梱施策のひとつです。
商品に添えられた一言メッセージがあるだけで、顧客は「大切に扱われている」と感じやすくなり、ブランドへの印象が大きく変わります。とくに以下のようなケースで効果を発揮します。
- ・D2Cや個人ブランドなど、顔の見える関係性を築きたいEC
- ・ギフト用途の多い商品(雑貨・アパレル・コスメなど)
- ・顧客単価やLTVが高く、ファン育成が重要な商材
サンクスカード設計のポイント
サンクスカードは「手書き風」であることが大切です。すべてを手書きにできない場合も、工夫次第で“温度感”を伝えることが可能です。
- ・印刷ベースでも、手書き風フォントを使って人の気配を演出
- ・「●●様」など、名前の手書きや個別メッセージを一部加える
- ・書き手(スタッフ)の顔写真や一言を載せて、共感を生む
- ・ブランドらしい口調や表現で、丁寧かつ自然な文面にする
- ・SNSのQRコードや、おすすめ商品の案内もさりげなく添える
「人が見える」「心が伝わる」ことがサンクスカードの最大の魅力です。小さな紙1枚でも、ブランドとの関係性を深める力を持っています。
実施時の注意点
温かみを与えるサンクスカードですが、形式的すぎたり手間がかかりすぎたりすると逆効果になることもあります。
- ・全員に同じ文面だと「作業的」と受け取られるリスクがある
- ・大量出荷時の負担が大きくなるため、対象や内容の絞り込みが必要
- ・字が読みづらい、インクがにじむなど品質面もチェックが必要
- ・スタッフの負担軽減のため、テンプレート+個別追記の仕組みが有効
大切なのは「伝わること」です。完璧でなくても、丁寧に届けられたメッセージは、顧客の心にしっかり残ります。
ECのクロスセル・アップセルのためによく使われる同梱物
クロスセル・アップセルの同梱物は、顧客単価の向上や新商品の認知拡大に直結する施策です。
関連商品のカタログやおすすめサンプル、まとめ買い案内、新商品の先行情報などを届けることで、「ついで買い」「次も欲しい」という購買行動を自然に引き出します。
次から詳しい内容を見ていきましょう。
関連商品のカタログやリーフレット
関連商品のカタログやリーフレットは、現在購入された商品に加えて「次に欲しくなる商品」を自然に提案できる同梱物であり、クロスセル・アップセルの定番施策のひとつです。
紙媒体ならではの一覧性と視認性を活かして、顧客に新しい気づきを与えることができ、「これもあるなら買ってみよう」という購入意欲を高める効果があります。とくに以下のようなケースで成果を上げやすくなります。
- ・複数の商品を組み合わせて使う用途がある(例:化粧品・調味料・文房具など)
- ・バリエーションやシリーズが豊富な商品ラインを展開している
- ・購入者の関心軸に沿ったレコメンドが可能な場合(例:目的別・季節別)
カタログ設計のポイント
関連商品カタログの効果を最大化するには、「誰に・何を・どう見せるか」を意識した設計が不可欠です。
- ・購入商品に関連したアイテムを中心にセレクトする
- ・「一緒に使うと効果的」「合わせ買いで送料無料」など明確な利点を示す
- ・QRコードで商品ページに誘導し、すぐ購入できる導線をつくる
- ・写真やコピーで使用シーンを具体的にイメージさせる
- ・裏面に次回購入特典やキャンペーン情報を掲載して再訪を促す
リーフレット1枚でも、目的を持って構成すれば、デジタル広告にはない“開封率の高さ”と“じっくり見てもらえる時間”を活用できます。
実施時の注意点
カタログやリーフレットは情報量が多い分、届け方やデザインによって効果に大きな差が出ます。
- ・一律の内容だと関心の薄い商品ばかりになり、逆効果になることも
- ・レイアウトが煩雑だと読まれずに捨てられてしまう
- ・QRコードのリンク切れや情報更新漏れに注意
- ・商品数が多すぎると選びにくく、行動につながらない場合もある
「この人にはこの情報が合う」と想定して設計されたリーフレットは、顧客の満足度と売上の両方を高める強力なツールとなります。
おすすめ商品のサンプル
おすすめ商品のサンプルは、まだ購入されたことのない商品を“試すきっかけ”として提供することで、クロスセル・アップセルを狙う非常に効果的な同梱施策のひとつです。
実際に体験してもらうことで興味関心が高まり、「これもいいかも」「今度はこれを買おう」といった自然な購買動機を生み出します。とくに以下のようなケースで効果が出やすくなります。
- ・味や使用感など、体験によって魅力が伝わる商品(食品・コスメなど)
- ・シリーズ展開されている商品や、バリエーションが多い商品
- ・新商品や季節限定商品など、まだ知られていないアイテム
サンプル設計のポイント
クロスセル・アップセルを狙うサンプルは、戦略的に設計することでより高い成果が期待できます。
- ・購入商品と関連性のあるアイテムを選ぶ(例:シャンプー購入者にトリートメントのサンプル)
- ・「このサンプルが気に入ったらこちらもチェック」などの導線を明記
- ・サンプルパッケージや案内カードにQRコードをつけ、すぐ購入できるようにする
- ・数量限定や先着プレゼントとして希少性を演出
- ・初回限定クーポンやレビュー特典とセットで設計し、行動につなげる
「まずは試してみて」という気軽なアプローチから、顧客の選択肢を広げていくことで、継続的な売上と商品理解の促進が図れます。
実施時の注意点
おすすめ商品のサンプル施策は効果的ですが、選定ミスや運用負荷の増加による注意点もあります。
- ・顧客にとって無関係な商品を同梱すると、かえって印象を悪くする
- ・サンプルのコストと配送コストが利益に与える影響を事前に計算する
- ・使用方法やアレルギー表示など、安全性の情報も忘れず明記する
- ・在庫や賞味期限の管理を適切に行い、ロスを防ぐ
正しく設計されたサンプルは、商品の価値を“体験”を通して伝えることができる、最も説得力のあるセールスツールになります。
セット購入やまとめ買い割引の案内
セット購入やまとめ買い割引の案内は、「今よりお得に買える選択肢」を提示することで、クロスセル・アップセルを自然に促す同梱施策のひとつです。
「どうせ使うなら多めに」「まとめて買った方がお得」といった心理に働きかけることで、客単価の向上や次回購入までの間隔延長が期待できます。とくに以下のようなケースで効果が出やすくなります。
- ・食品・日用品・サプリなど、定期的に消費される商材
- ・複数パターンを持って楽しむファッションや雑貨商品
- ・使用頻度の高い消耗品やリフィル型の商品
案内設計のポイント
セット割・まとめ買いの案内は、顧客に「買い足したくなる理由」をわかりやすく伝えることが大切です。
- ・人気商品のセット販売を紹介し「これだけで完結します」と訴求
- ・「通常購入より●%お得」など、金額メリットを明確に記載
- ・購入者の使用シーンに合わせたまとめ買いパターンを提案
- ・案内チラシにQRコードをつけて、特設ページへ簡単に誘導
- ・数量限定や期間限定の割引として、今すぐ買いたくなる演出を
顧客の「もっと使いたい」気持ちと「どうせならお得に」という心理を同時に刺激することで、売上の最大化が期待できます。
実施時の注意点
割引施策は魅力的ですが、条件設計や見せ方によっては利益やブランド印象に悪影響を与えることもあります。
- ・割引率が高すぎると利益を圧迫しやすいので事前にシミュレーションを
- ・複雑な割引条件は伝わりにくく、離脱を招くことがある
- ・在庫リスクやセット構成の在庫管理に注意が必要
- ・特典ばかりが目立ち、商品価値が伝わらない場合もある
「まとめて買ってよかった」「これなら次も買いたい」と思ってもらえるよう、わかりやすく、魅力的に、かつ利益を意識した設計が成功のカギになります。
新商品の先行案内
新商品の先行案内は、「いち早く新しい情報を届ける特別感」によって、顧客の興味を引き出し、クロスセル・アップセルを促進する同梱施策のひとつです。
とくに既存商品を購入したばかりの顧客にとって、関連性の高い新商品の情報は「次はこれも試してみよう」という自然な動機づけになります。以下のようなケースで効果が高まります。
- ・定期的に新商品をリリースしているブランド
- ・シリーズ展開や季節ごとのバリエーションがある商品
- ・既存顧客との関係を深め、LTVを高めたい商材
案内設計のポイント
新商品の案内は、ただ「発売されます」と伝えるのではなく、顧客が「自分だけが知っている」「早く試したい」と思える仕掛けが重要です。
- ・「先行案内」「限定情報」「一部のお客様限定」などの特別感を演出
- ・新商品の魅力を簡潔に伝えるコピーやビジュアルを活用
- ・購入者の関心とリンクする商品をピックアップして掲載
- ・先行予約や先行販売ページへのQRコードをつけて即行動につなげる
- ・先行購入者限定の特典や割引を組み合わせると、転換率が向上
顧客に「自分は特別扱いされている」と感じてもらえると、ブランドへの信頼とロイヤリティが自然と高まり、次の購入にもつながります。
実施時の注意点
新商品の先行案内は、期待感を生む一方で、実施タイミングや対象設定を誤ると逆効果になる可能性があります。
- ・案内時点で詳細や購入ページが準備されていないと混乱を招く
- ・すでにサイトなどで一般公開されている内容だと特別感が薄れる
- ・すべての顧客に配ると「自分に関係ない情報」として無視されがち
- ・頻度が高すぎると希少性が薄れ、効果が鈍化する
「あなたにいち早くお届けする」という姿勢が伝わるよう、ターゲティングとタイミングを意識した設計が成功のカギとなります。
ECのレビュー促進のためによく使われる同梱物
レビューはECにおける「信頼の資産」であり、購入を検討する他のユーザーに強い影響を与えます。
そこで役立つのが、レビュー投稿を促す同梱物です。QRコード付きカードやレビュー特典クーポン、他の顧客の声をまとめたブックレットなどは、投稿のハードルを下げると同時に、顧客の声を資産として蓄積するきっかけになります。
次から詳しい内容を見ていきましょう。
レビュー投稿用のQRコード付きカード
レビュー投稿用のQRコード付きカードは、購入者にレビュー投稿を促すための同梱物として非常に効果的なツールです。
商品を受け取った直後の顧客は、購入体験が新鮮な状態にあり、そのタイミングでレビュー依頼が届くと反応率が高まります。スマホで簡単にアクセスできるQRコードを使うことで、レビューのハードルを下げ、投稿数の増加が期待できます。とくに以下のようなケースで効果が出やすくなります。
- ・商品レビューが購買判断に大きく影響する商材(コスメ・家電・サプリなど)
- ・レビュー投稿者に特典(ポイント・割引など)を用意しているEC
- ・レビュー数を増やしてCVRを高めたい新商品・季節商品の販売時期
カード設計のポイント
レビューを書いてもらうためには、「簡単・すぐできる・得になる」と感じてもらう仕組みづくりが大切です。
- ・QRコードを印刷し、スマホでワンタップ投稿ができるようにする
- ・「レビュー投稿はこちら」のように、行動を明確に示すコピーを添える
- ・レビュー投稿のメリット(例:100ポイント付与、抽選でプレゼント)を明記
- ・丁寧で親しみのある言葉づかいで「お願い」する形式に
- ・レビューの例文や記入のヒントを簡潔に書くことで、心理的ハードルを下げる
レビューはECにとって貴重な資産。顧客にとっても「意見が反映される」「他の人の役に立つ」と感じられる設計にすることで、自然な投稿につながります。
実施時の注意点
レビューカードは効果的ですが、やり方を誤ると逆効果になる場合もあるため注意が必要です。
- ・過度にレビューを催促すると「押しつけがましい」と感じられることがある
- ・QRコードのリンク切れや誤リンクは機会損失につながるため定期チェックが必須
- ・インセンティブ付きレビューはガイドライン違反になる場合があるため、内容に注意
- ・投稿完了後の導線(サンクスページや特典付与)の整備も忘れずに
「レビューが書きやすい」「レビューを書きたくなる」環境を用意することが、投稿率アップと顧客との信頼関係づくりの両方につながります。
レビュー投稿で次回使えるクーポン案内
レビュー投稿で次回使えるクーポン案内は、「レビューを書くだけで得をする」体験を提供し、レビュー数とリピート率の両方を高めることができる同梱施策のひとつです。
購入直後の顧客に対し、「レビューを書いていただいた方には次回使える●%OFFクーポンを進呈!」と案内することで、レビューという行動を自然に促すと同時に、次回購入の動機づけにもつながります。以下のようなケースで効果を発揮しやすくなります。
- ・商品レビューが売上に影響する商品(美容・食品・雑貨など)
- ・リピート性の高い消耗品や定期購入商品
- ・レビュー数を増やしたい新商品やキャンペーン期間中の商品
クーポン案内の設計ポイント
レビュー投稿とクーポン取得をスムーズにつなげるためには、行動の流れが明確で、わかりやすい設計が必要です。
- ・「レビュー投稿で●●円OFFクーポン進呈!」というシンプルな訴求
- ・QRコードを掲載し、投稿フォームや詳細案内ページにすぐアクセス可能に
- ・レビュー内容に関係なくクーポンを付与することで心理的ハードルを下げる
- ・クーポンの使用期限を設け、早期の再訪を促す
- ・付与されたクーポンの使い方・利用条件をカード上で明記
レビューはユーザー目線の信頼材料としてECにおける強力な武器となるため、レビュー投稿を「お得な体験」として演出するのが鍵です。
実施時の注意点
レビュー投稿と引き換えのクーポンは効果的ですが、設計を誤ると信頼性や利益への影響も出てくるため注意が必要です。
- ・金額や条件が複雑だと離脱の原因になるため、明確で簡単な内容に
- ・「好意的なレビューを条件にする」と誤解されないよう、言い回しに配慮
- ・インセンティブによるレビュー施策は、モール規約やガイドラインに準拠する
- ・投稿確認・クーポン配布の運用フローを明確にし、ミスや遅延を防ぐ
レビュー数と再購入率の両方を同時に高めることができるこの施策は、適切に設計すればEC運営にとって非常にコストパフォーマンスの高い手法になります。
顧客の声を掲載したミニブックレット
顧客の声を掲載したミニブックレットは、実際に商品を使用した人のリアルな体験談をまとめることで、新たな購入者の共感を呼び、レビュー投稿への心理的ハードルを下げる同梱施策のひとつです。
「この人の感想に共感した」「私も感じたことを伝えたい」といった感情を引き出すことで、自発的なレビュー投稿につながるだけでなく、商品の信頼性や満足度を高める効果もあります。特に以下のようなケースで効果が出やすくなります。
- ・レビューによる信頼が購入に直結する商品(美容・健康・生活雑貨など)
- ・ストーリー性のあるブランドやD2C商品
- ・使い方や効果に個人差が出やすい商品
ブックレット設計のポイント
レビューの掲載は、ただ羅列するだけでなく、「読む楽しさ」や「共感のしやすさ」を意識した構成が重要です。
- ・年齢・性別・用途が異なる複数の顧客の声を掲載し、読者の幅を広げる
- ・写真付きコメントや手書き風レビューなど、リアリティを感じる見せ方にする
- ・「◯◯で悩んでいた私が、こう変わった」などストーリー性のある構成に
- ・「あなたの声もぜひ聞かせてください」という一言と投稿ページQRコードを記載
- ・投稿者の許可を得た「受賞レビュー」や「人気レビュー」の紹介も効果的
ブックレットを通じて「誰かの声が、私の背中を押してくれた」という共感体験を提供できれば、次は自分が誰かの役に立ちたいという投稿意欲につながります。
実施時の注意点
レビュー掲載型ブックレットは信頼性が鍵となるため、内容や表現方法に注意が必要です。
- ・実際のレビュー内容を正確に反映し、誇張表現や虚偽は避ける
- ・掲載許可を得ていないレビューは個人情報や表現の扱いに十分配慮
- ・内容が長すぎたりデザインがごちゃついていると読まれにくくなる
- ・同じような意見ばかりだと「仕込み感」が出て信頼を失う可能性も
“お客様の声”は、売上を伸ばすための最強の説得材料。ミニブックレットを通じて「あなたの声も大切です」と伝えることで、顧客との信頼関係を築きながら、レビュー数の向上が見込めます。
ECの同梱物で成功した事例
ここでは、実際にコスメ・食品・アパレル・ペット用品といった分野で成果を上げた事例を紹介します。
コスメECを運営するA社
・リピート購入率が低く、顧客が定着しない
・商品ラインナップの幅広さが十分に伝わっていない
A社は、初回購入者に「次回使える割引クーポン」と「新商品のサンプル」を同梱しました。顧客はサンプルを試すことでブランド内の別商品にも関心を持ち、さらにお得に購入できる仕組みがあったことで、2回目以降の購入率が大幅に上昇しました。結果として、LTV向上に直結する成功事例となりました。
食品ECを運営するB社
・一度きりの購入で終わる顧客が多い
・商品のこだわりや背景が十分に伝わっていない
B社は、商品と一緒に「生産者インタビュー冊子」と「おすすめレシピカード」を同梱しました。顧客は生産者の想いや活用方法を知ることで商品に愛着を持ち、自然とリピート購入につながりました。ブランドストーリーを伝える同梱物が、ファン化を加速させた成功事例です。
アパレルECを運営するC社
・返品率が高く、サイズや素材感の不安が多い
・次回購入への動機付けが弱い
C社は、注文商品と一緒に「次回購入時に使える送料無料クーポン」と「生地サンプル冊子」を同梱しました。顧客は実際に生地に触れて安心感を得られるようになり、返品率が改善。また送料無料特典がリピート購入を後押しし、売上の安定化に成功しました。
ペット用品ECを運営するD社
・顧客とのコミュニケーションが希薄
・SNSでの拡散や口コミが少ない
D社は、商品と一緒に「飼い主向けお役立ち冊子」と「ペット用おやつのサンプル」を同梱しました。さらに「SNS投稿キャンペーンカード」も添えて拡散を促進。その結果、SNSでの投稿数が増加し、新規顧客獲得にも成功。既存顧客からの満足度も高まり、ロイヤル顧客の増加につながりました。
EC×同梱物の効果測定方法
同梱物は「入れること」が目的ではなく、「どんな成果につながったか」を確認してこそ意味があります。
クーポン利用率やサンプル後の購入率、アンケートによる顧客の反応、LTVや再購入率の変化など、複数の視点で測定することで、施策の有効性を正しく判断できます。
次から詳しい内容を見ていきましょう。
クーポンの利用率を測る
ECにおいて同梱物の効果を可視化するうえで、もっとも取り組みやすい方法が「クーポンの利用率を測る」ことです。
同梱物に印刷したクーポンコードを使って、再購入時の割引や特典を提供することで、そのクーポンが何回利用されたかを追跡できます。
この方法のメリットは、数字で明確に成果を把握できること。たとえば「DOKON15」など、同梱専用のクーポンコードを発行すれば、他の施策との混同も避けられ、同梱物単体の効果を純粋に測定できます。
また、クーポンの使用タイミングや購入商品などもあわせて分析することで、
・どのターゲット層に響いたのか
・どの価格帯の商品と相性がよかったか
・リピートまでにかかる平均日数はどのくらいか
など、より深い洞察が得られるのも魅力です。
クーポンの有効期限や割引率を変えながらABテストをおこなえば、同梱物としてのベストなオファー条件も見えてきます。
「入れるだけ」で終わらず、「どう使われたか」を数字で捉えることが、次の改善につながる重要な一歩です。
サンプル同梱後の購入行動を追う
サンプル(試供品)を同梱する施策は、将来的な購入につながる可能性が高く、ECにおいて有効な販促手段のひとつです。
しかし、「ただ配るだけ」では効果は不明確なまま。その後に実際の購入行動につながったかどうかを追跡することで、施策の成果を正しく測定できます。
たとえば、Aという商品を購入した人に、Bという商品のサンプルを同梱した場合、その後一定期間内にBを購入した人の割合(転換率)を記録することで、サンプルの訴求力を具体的に評価できます。
このとき、同梱ありのグループと同梱なしのグループに分けてABテスト形式で比較すれば、より信頼性の高いデータが得られます。
また、以下のようなデータをあわせて見ることで、さらに分析の精度が上がります。
- ・サンプルを同梱した月の商品別売上
- ・初回購入から再購入までの平均期間
- ・再購入者のLTV(顧客生涯価値)
サンプルの内容やパッケージ、同梱するタイミングなどによっても結果は大きく変わるため、複数パターンを検証していくことが大切です。
「試してもらえば気に入ってもらえる」商品は、サンプル同梱→再購入の流れを設計し、しっかりと効果検証まで行うことで売上アップにつながります。
アンケートで顧客の反応を確認する
同梱物の効果を測る方法として、アンケートによる顧客の声の収集はとても有効です。
クーポンの使用率や再購入率といった数字では見えにくい、顧客の感情や印象を把握できるからです。
たとえば、同梱物に対して以下のような問いを設定したアンケートを送ることで、反応を可視化できます。
- ・同梱物を開封したかどうか
- ・内容が役に立ったかどうか
- ・好印象を持ったポイント
- ・改善してほしい点
これにより、「ただ同梱されていた」ではなく、「印象に残った」「次回購入に影響した」などの具体的なフィードバックを得ることができます。
また、回答率を高めるためには、アンケートの設問数を少なくしたり、回答者限定のクーポンやポイントなどのインセンティブを用意するのが効果的です。
集まったデータは、次回以降の同梱物改善や、ターゲットごとの最適化にも活用できます。
顧客のリアルな声を拾うことで、「自己満足型の同梱物」から「顧客満足につながる同梱物」へと進化させるヒントが見つかります。
LTVや再購入率に与える影響を見る
同梱物の効果を中長期的に測定したい場合、「LTV(顧客生涯価値)」や「再購入率」に与える影響を確認することが重要です。
LTVとは、ひとりの顧客が生涯を通じて自社にもたらす利益の総額を指します。つまり、顧客との関係が長く、繰り返し購入されるほどLTVは高くなります。
同梱物を活用して接点を増やすことが、ブランドへの愛着や再訪問の動機づけになり、結果としてLTVや再購入率の向上につながるケースがあります。
たとえば以下のような視点でデータを比較・分析すると効果が見えてきます。
- ・同梱物を送ったグループと、送らなかったグループの再購入率
- ・LTVの推移(一定期間内の平均購入回数や購入単価)
- ・初回購入後の継続率や離脱率
このように継続的なデータを追うことで、同梱物が単なる販促ツールではなく、顧客との関係性を深める要素として機能しているかどうかを見極めることができます。
とくに高単価商品や定期購入型の商品を扱うECでは、LTVや再購入率の改善が売上インパクトに直結するため、施策としての優先度も高くなります。
定期的に分析を行い、内容やタイミングを最適化することで、同梱物が「一度きりの販促」から「長く愛される仕組み」へと進化していきます。
EC×同梱物の法的・規制面で注意すること
同梱物を活用する際には、販促効果だけでなく法的な規制にも配慮する必要があります。
景品表示法による景品類の上限、薬機法による化粧品・医薬品の表現規制、個人情報保護法に基づくデータの扱い、さらには著作権・商標権の確認など、多方面に注意が必要です。
次から詳しい内容を見ていきましょう。
景品表示法の制限に注意
同梱物としてプレゼントや試供品などを提供する場合、「景品表示法(景表法)」が適用される可能性があります。
とくに、購入特典として提供する同梱物は「景品類」と見なされ、景品額の上限が定められています。
例えば、販売価格が1,000円以上の場合、景品の上限は「取引価額の20%かつ2万円まで」など、明確なルールがあります。
これを超えると違法になるため、特典を設定する際には必ず金額や条件を確認しましょう。
医薬品・化粧品の試供品には薬機法が関わる
医薬部外品や化粧品などを同梱する場合、「薬機法(旧:薬事法)」の規制を受けます。
製品ラベルや表示内容に虚偽・誇大な表現がないか、販売目的で配布して良い種類の製品かなど、法的基準を満たしている必要があります。
特に、化粧品の効能を過剰にうたう文言や、医療効果を想起させる表現には注意が必要です。
個人情報の取り扱いと表示物の配慮
同梱物にアンケート用紙や会員登録の誘導が含まれる場合、個人情報の取得に関するルール(個人情報保護法)を守る必要があります。
利用目的を明示しないで個人情報を取得するのはNGです。
また、送り状や納品書などに記載される情報の取り扱いにも注意し、不要な個人情報を印字しないようにしましょう。
商標・著作権の侵害に注意
チラシや冊子、イラストなどを同梱する場合、使用しているロゴ・写真・イラスト・文章などが著作権や商標権を侵害していないか確認が必要です。
たとえ外注したデザイナーが制作したものであっても、権利関係が曖昧な素材を使っていれば企業として責任を問われるリスクがあります。
まとめ
ECの同梱物とは、ネット通販の商品に同封される印刷物やサンプル、ノベルティなどを指し、単なるおまけではなく顧客体験を豊かにし、リピート購入やファン化を促す重要な役割を持っています。
たとえばクーポンや試供品で次回購入を後押ししたり、サンクスメッセージやブランドストーリーで信頼感を高めたりできます。メリットとしては、リピート購入を促す導線作り、顧客との信頼関係の強化、ブランドイメージ向上、クロスセルやアップセルの機会創出、さらには正しい使い方や注意点を伝えることでクレームや返品を減らす効果が挙げられます。
一方で、印刷費や作業工数、物流コストといった負担が増える点、内容によってはゴミ扱いされるリスクやブランドイメージを損なう可能性がある点、管理や在庫の手間が増す点、効果測定がしにくい点などデメリットも存在します。
そのため、同梱物を設計する際は「誰に、何を、どのような目的で届けるか」を明確にし、ブランドメッセージとの一貫性を保ちながら顧客体験を高めることが大切です。
また、クーポン利用率やサンプル後の購入行動、アンケート調査、LTVや再購入率の変化などを追うことで効果を数値化し、改善を繰り返すことが成功につながります。
実際にクーポンやサンプルを活用してリピート率を向上させた事例や、冊子やレシピカードでファン化につなげた事例もあり、同梱物はECにおける強力なマーケティング手法といえます。